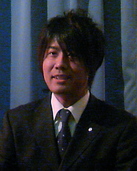皇紀2673年(平成25年)5月30日
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2013052600172……
▲時事通信:米兵、仏女性を性的はけ口に=レイプも多発-大戦中の欧州
大東亜戦争で任地に赴いたわが国の先人たちが一人残らず戦場で高慢な性行為に耽っていたかのような冒涜に及ぶいわゆる「従軍」慰安婦発言は、同時に当時の朝鮮人女性をも愚弄するものであると私は何度も指摘してきましたが、韓国が賠償金目当てに始めた「対外喧伝行為(ロビー活動)」に侵された現在、欧米諸国に対して私たちはどうすべきでしょうか。
少しばかり私たちはこの問題に神経を尖らせ過ぎなのですが、今さら「従軍強制」を否定しても、なかったことが事実にもかかわらず、欧米諸国の国民や政府は聞く耳を持ちません。これはかつて申した通り、私がはっきりと欧州某国の政府関係者に言われました。
彼らは韓国の国民や政府を一切支持していませんが、それとは別に「日本政府自身が一度認めた『人権問題』をなかったことにするのは絶対に賛同出来ない。賛同したら今度は自国が非難される」と言うのです。それほど「河野談話」は恐ろしい間違いであり、今後私たちは二度とこのような「妥協・屈服・事なかれ」を政府に許してはなりません。
そこで、私が徹底的に指弾しながらも唯一点正しい部分と指摘した大阪市の橋下徹市長による「わが国だけが批判されることではない」ことだと喧伝するのです。
朝鮮戦争下の韓国軍も慰安婦を利用しましたが、越国(ヴェト・ナム)戦争では韓国軍兵士による強姦の事例も多く報告されており、そもそも越戦に於ける米軍兵士の保養所として開けたのが泰王国(タイ)のパッタヤーでした。ここの現実を目の当たりにされたことがあるなら、どのように開けたのかすぐにお分かりでしょう。
さらに、米ウィスコンシン大学のメアリー・ロバーツ教授は第二次世界大戦中の仏国で、進駐した米軍の兵士たちが仏国人女性を買春の対象にしたり、強姦したこともあった事実を報告しています。
それを申せば独伊に対しても同様の事例があり、私たちにとって明白なのは、わが国占領統治下で日本人女性が汚されないよう「性的防波堤のため」と内務省通牒で設置された特殊慰安施設を、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が認めてしまっているのです。
私たちは決して米国の先人たちを冒涜したくありません。彼らは大東亜戦時の敵でしたが、いたずらにその名誉を傷つけることが許されるはずなどないのです。これが平気な韓国と、わが国とでは性質が全く違います。
ですが、韓国の喧伝行為を許してわが国を攻撃すると言うのなら、出したくもない米軍兵士と性の話も出さざるを得ないのです。
本来であれば、私たちは一昔前までどの国でも人身売買が横行していた事実を皆で反省し、今も行なわれている可能性と戦うべきであり、過去の現実を他国のせいにして現在の関係を悪化させるべきではありません。
わが国も「口減らし」のために泣く泣く息子を丁稚奉公に出し、娘を置屋に売った親もいた過去はありますが、妓生検番に娘を売ったのは朝鮮人自身です。その過去を羞じると言うのなら、今しなければよいではありませんか。
対米従属の許せないのは、自分たちで形勢を逆転させる策を持たないことであり、仮に米政府から「河野談話を見直すな」と言われても、安倍晋三首相はこの問題に取り組むべきです。
分類:日本関連, 欧州露・南北米関連 | コメント4件 »
皇紀2673年(平成25年)5月29日
http://buzzap.jp/news/20130523-sbm-75mbps-area/
▲BUZZAP!:ソフトバンク版iPhone 5向けLTE、75Mbps対応エリアの人口カバー率はわずか1%
私はこれまで何度も「ソフトバンク」に係る問題を取り上げてきましたが、先週の報道で「au KDDI」利用者に衝撃が走りました。それは、アップル社の端末「iPhone 5」向けLTE(高速データ通信規格)の七十五Mbps(メガビット=通信速度の単位)対応地域の実人口カバー率が十四%しかなく、広告宣伝と違うため、KDDIに対して消費者庁から措置命令が下ったというものです。
広告には「実人口カバー率が九十六%」とあったのですが、それは恐らく三十七.五Mbps対応地域を含めたものだったはずで、KDDIでは個別機種ごとに対応地域を出していたわけではありませんから、少し消費者庁の指摘は厳しすぎるのではないかと思われます。
仮にもここまで厳格化するのであれば、それは消費者にとって商品選択の情報を豊かにしてくれますから、是非ともソフトバンクにも措置命令を下して欲しいものです。
その根拠は、IT関連の情報を扱う「バザップ!」が示している通りで、算出方法に多少の違いがあることを差し引いても、ソフトバンクが広告で謳っていることこそおかしいと指弾せざるを得ません。
彼らが最近「一番繋がるようになった」と強調した映像広告を大量に投入しているのは、皆様もご存知の通りです。しかし、ソフトバンクの七十五Mbps対応地域こそあまりにも貧弱で、全人口に対してたった一.二三%しかカバー出来ていません。
にもかかわらず、KDDIへの措置命令が大きく報じられ、NTTドコモはともかく、よく繋がることを棒グラフにまで表した広告をばら撒くソフトバンクばかりがあたかも本当に繋がりやすく(早く)なったかのような紛らわしい印象を私たちに与えています。
私たちが騙されなければそれでよいのですが、報道各社がソフトバンクの問題に限って報じたがらず、同業他社の問題ならばすぐに伝えるのはなぜでしょうか。そもそもKDDIに対する行政指導を煽ったのはどなたでしょうか。
何度も申しますが、この会社は他社の買収を繰り返して資金を調達してきた「自転車操業」状態にあり、金融機関にとってもはや潰したくても潰せない存在です。彼らはそうなることを狙って増資してきたのでしょうが、メガソーラーといい、ほとんど実体がありません。
北朝鮮関連資金を叩き潰している最中の米政府に、いつ手をかけられるかが見ものでしょう。
分類:亜州・太平洋関連, 日本関連 | コメント4件 »
皇紀2673年(平成25年)5月28日
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2400E_U3A……
▲日本經濟新聞:マイナンバー法成立 税・年金を16年から一元管理
年金などの社会保障や税の共通番号(マイナンバー)法は二十四日の参議院本会議で可決、成立しました。私たち一人一人に個人番号が割り当てられる制度は平成二十八年一月から始まり、行政手続きが大幅に簡素化されます。
これからは役所でいろいろ書かされなくてもよくなり、とても便利にな……、いや、ちょっと待った! 日本經濟新聞社の配信記事にある「特定個人情報保護委員会」とは何でしょうか。私が危険視している「番号情報保護委員会、いわゆる三条委員会」のことです。
従来私は「限られた項目を対象にした共通番号制」の導入の提言を検討してきました。それは、財務省から徴税機関である国税庁を切り離し、消費税増税を押し通して政権を制御してきたことへの厳罰の布石とする目的もあったからです。
ところが、いざ出来たこの法案に内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づく三条委員会の設置が明記されて話は全く変わってしまいました。最初の法案にはなかったものです。創価学会=公明党が修正を要求したと聞いています。
この法案の主旨に反対したのは日本共産党らですから、創価学会と共通するのは、個人情報を一括で管理・掌握して欲しくない事情があることでしょう。よって公明党は、これをさらに監視または監督する独立した機関の設置を求めたものと考えられます。
法に規定された所掌事務からして、これが「人権擁護、或いは人権救済の法案」に出てくる三条委員会とは別の性質のものであることは分かりますが、しかし、国籍条項がないのは同じであり、その気になれば委員会が個人の職歴や婚姻などに関するあらゆる情報を一手に掌握し、それを目的外使用する危険性は捨て切れません。
また、IT業界ではシステム構築などの大型事業が出てくることに期待する声も出始めていますが、一体どこが受注するのでしょうか。まさか「韓国のサーバで管理」するような企業にやられては困ります。
政府ともう一つの強力な権力がここまでの個人情報の一元管理に手をかけたということは、思想統制や言論統制といった、やはり法務省が目論んできた人権擁護・人権救済の名を借りたのと同じ目的が潜んでいると申して過言ではありません。
運用に間違いがないよう設置されるらしい委員会の運営こそ厳格化すべきであり、個人情報の持ち出しや勝手な調査、目的外使用などに対して量刑(刑法としての厳罰)を定めた法の改正を求めましょう。
皆さん、占領憲法(日本国憲法)下で集約される個人情報はどこへ行くか分かりませんよ。
分類:日本関連 | コメント5件 »
皇紀2673年(平成25年)5月27日
http://www.47news.jp/CN/201305/CN201305240100……
▲共同通信:飯島参与、韓国紙報道を否定 首相の訪朝可能性で
韓国の権哲賢前駐日大使は朝鮮日報(韓国)の取材に対し、「安倍晋三首相が早ければ今月末から六月初めにも訪朝する可能性が高い」などと根拠もないまま述べました。
これについて、訪朝した飯島勲内閣官房参与は二十四日午前、記者団に「そんなことあるわけない」と不快感を示し、「日朝交渉がうまくいかないようにするための妨害工作だ」と批判しています。
今回の顛末は、私が五月二十一日記事に述べた通りです。わが国政府は韓国政府にほとんど訪朝の成果を漏らしていません。しかし、米政府とは情報を共有しました。
よって権前大使程度の人物が日朝交渉の詰めの結果を知っているはずなどないのです。幼稚な知ったかぶりか、或いは飯島参与の指摘通り「妨害工作」以外にありません。
たとえ安倍首相の訪朝が来月中にあるとしても、それを事前に触れ回らない約束になっています。私は「六月中に動く」と聞きましたが、誰が何がどう動くのかさっぱり分かりませんし、当然知りません。うっかり申せば殺されます。
いえ、殺されそうになっても申せないのは、すべて日本国民拉致被害者と特定失踪者の皆さんのためであり、当然ではありませんか。中共に寄って行って持ち上げられ、挙げ句に半島ごと呑み込まれる運命を選択しつつある韓国の前大使には、私たちの生命の尊厳などどうでもよいことなのでしょう。
彼らがこのような態度を撤回しない限り、かえすがえすも日韓首脳会談を開くべきではありません。韓国は自分たちの大統領よりも先に金正恩第一書記が安倍首相と首脳会談を開くことが悔しくて我慢ならないのです。
米「ニューズウィーク」日本版五月二十八日号の特集ではありませんが、韓国「日本叩き」の代償たる自滅外交、歴史問題を口実に「日本外し」を目論む韓国の「近視眼外交」の末路を彼ら自身が見ることになるのか、それとも回避しうるのか、私たちは極めて冷めた目でこれを眺めることになるでしょう。
焦ってはいけません。残念ですがそれでよいのです。
分類:亜州・太平洋関連, 日本関連 | コメント1件 »
皇紀2673年(平成25年)5月26日
http://www.yaeyama-nippo.com/2013/05/15/……
▲八重山日報:中国公船に包囲された
沖縄県石垣市の漁船「高洲丸」は今月十三日午後、同市尖閣諸島南小島の東南約二キロメートルの海上で、領海侵犯してきた三隻の中共海洋監視船に取り囲まれました。
第十一管区海上保安庁の巡視船は中共公船を取り締まるべく、高洲丸との間に割って入り、その甲斐あってか中共側は六時間後、わが国領海からそのまま退去しています。
高洲丸に乗っていたのは高江洲正一船長を筆頭に、かねてより「尖閣防衛」を掲げて戦い続けてきた仲間均石垣市議会議員と、伊良皆高信石垣市議会議長、さらに記事にしてくれた八重山日報の仲新城誠記者ら六人です。
かつては防衛意思薄弱なわが国政府の命令により、海保に排除されてきた仲間議員でしたが、現在の状況は全く変わっています。
仲間議員が「ここは日本の領海だ。私は逃げない」と宣言すれば、海保側も決して退去を命じず、懸命に中共の「海監六十六」らを近づけさせないよう務めてくれました。
この監視船はあろうことかわが国の領海に頻繁に侵入し、沖縄県内の漁民たちを威嚇しています。それを見て見ぬ振りして「日中関係の改善」などと机上の空論を述べるなら、それは国民の身体・安全・生命・財産をないがしろにしようとする「人殺し」の戯言に他なりません。
私が講演会にお招きした仲間議員にお会いしてまず思いましたのは、とても優しい目をされていることでした。これほどの強い意志をもって私たちの領土・領海を守ろうと、中共からの侵入者と戦い、政府と戦い、司法と戦ってきた仲間議員がとても優しいのは、私たちの命と暮らしを守ろうとしているからに違いありません。
今日もわが国を脅かす矮小な侵入者どもがいます。そして、人知れず奴らから漁師や地元議員たちがわが国を守ってくれているのです。そのことを私たちは決して忘れてはなりません。
分類:日本関連 | コメント2件 »