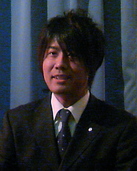皇紀2674年(平成26年)2月15日
http://diamond.jp/articles/-/47246
▲週刊ダイヤモンド:東大ベンチャーがグーグルの手に 突きつけられた日本の成長課題
昨年末に開かれた米国防総省国防高等研究計画局(DARPA)主催の災害救助ロボット・コンテストで、東京大学発のヴェンチャー企業「シャフト」が首位に立ち、彼らはあっという間に米検索大手「グーグル」に買収されました。
東日本大震災直後、災害救助や原子炉内の事故に対応出来るロボットの開発を求めた声を、霞ヶ関のどこででも聞いたことがないとは言わせません。
複数の然るべき人物が指示を出したはずですが、実はそこで政府も開発を支援していた技術の実用化を前にして、放り出した経済産業省の罪はとてつもなく重いのです。
週刊ダイヤモンドの記事にはありませんが、政府系ファンドの産業革新機構も、同業の「スキューズ」への出資は決めたくせに、「本当は日本で資金調達したかった」と振り返った加藤崇氏を袖にしました。
シャフトは、実用化の段階になって資金を出し渋った政府の非情な後ろ姿と、先見性の欠片もないわが国財界に巣食う老人たちを見つめながら、背に腹はかえられず、米国のヴェンチャー・キャピタルに身を売るしかなかったのです。
わが国が開発を支援し、事実上世界一になった日本人の技術は、こうして米国に流出します。ここに、私が何度も申してきた「安倍政権の成長戦略の中身のなさ」が表れているのです。
現下の雇用や賃金の問題も、このままでは改善しません。全て繋がっている問題です。まずはシャフト買収に対する問題意識を政府に提起する必要がありますので、国会の予算委員会ででも取り上げてもらいましょう。
分類:日本関連 | コメント2件 »
皇紀2674年(平成26年)2月14日
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYEA1C01P2……
▲ロイター:移民受け入れの是非、国民的議論を経て検討すべき=安倍首相
http://jp.reuters.com/article/jp_column/idJPTYEA1B05R20140212
▲ロイター:コラム スイス国民投票が問いかけた「EUの未来」
衆議院予算委員会 十三日午前 「移民一千万人受け入れ」を掲げてきた民主党の古川元久衆議院議員の質疑 安倍晋三首相の答弁「わが国の将来の形や国民生活全体に関する問題として、国民的議論を経た上で、多様な角度から検討していく必要がある」
瑞国(スイス)では、九日に実施された国民投票の結果、移民流入を厳しく制限することに決まりました。仏独英など欧州各国では、移民問題が激しい暴動を発生させており、人をまるで「モノ」のように輸入する移民政策が、各国民の雇用や治安に対する著しい不安を掻き立てています。
安倍首相も、労働人口の減少が与える経済成長への影響を述べていますが、この観点から移民政策を進めた国は、軒並み国民生活を混乱させてきました。
露国のウラジーミル・プーチン大統領が中共との関係に於いて一線を引いていることは、私がここで何度も申しましたが、露国にとって露中国境最大の懸念は、中共側の一億人規模の人口です。彼はこれが脅威になることをよく知っています。
政府が国民的議論を見るというのですから、私たちは自らの考えを声に出していかなければなりません。わが国には、特別永住者という「人種特定政策」が存在します。そもそも移民を受け入れられる状態なのかどうか、多様な角度から検討しましょう。
分類:日本関連, 欧州露・南北米関連 | コメント3件 »
皇紀2674年(平成26年)2月13日
http://sankei.jp.msn.com/world/news/140212/kor140212……
▲産經新聞:村山元首相の面目丸つぶれ 韓国の慰安婦支援団体 「大きな傷与えた政治家」と批判
安倍晋三首相が靖國神社を参拝したことに対し、「国を売る行為だ」と批判した村山富市元首相こそ、いろいろな考え方があるにせよ、多くの私たち国民の存在を貶め、国を売った為政者でした。
韓国人慰安婦については、事実確認を著しく怠ったことが既に発覚している宮澤内閣の河野洋平官房長官談話(河野談話)が諸悪の根源であり、のちの村山首相談話は、当時政権奪還に執着していた自民党と担がれた旧日本社会党の「思い込みの合作」だったのです。
そして、猜疑心からくる歪んだ「善人願望」によって発せられた村山元首相の言葉は、結局のところ、日韓双方から「恨み節」を浴びせられたのでした。彼が韓国人女性からの問いかけを無視し、このように非難までされたことを、私たちははっきりと記憶しておくべきです。
韓国挺身隊問題対策協議会の目的は、巨額の「賠償金」と称するカネを、国際法上有効な日韓請求権協定を反故にしてでも私たちの税金からむしり取ることであり、出来るだけ「反日」を継続させることに違いありません。
自民党は、なぜ河野元官房長官の国会参考人招致を拒否したのですか? 事情は分かりますが、何度でも申します。まず河野談話の根拠となった杜撰極まりない調査報告書を、私たちは政府に全て公開させましょう。
分類:亜州・太平洋関連, 日本関連 | コメント4件 »
皇紀2674年(平成26年)2月12日
http://sankei.jp.msn.com/world/news/140211/amr140211……
▲産經新聞:日本海「普遍的に受け入れられてない」NY州議、「東海」併記法案提出正式発表
日本海呼称問題を起こされた経緯は以前に申し上げた通りですが、早い話が「カネの問題」です。まさか「高尚な歴史問題」ではありません。まして米連邦政府にとっては、実務上の問題であって「歴史」とは全く関係がないのです。
しかし、カネの問題である以上、州議会議員の単位だけでなく、連邦議会の上下両院議員も汚染されていくでしょう。それほど中韓の現地「米国侵略」「日米離間」工作は進んでいます。
米国の政治家は、韓国人を利用する中共に内部から侵略されようとしていることに気づいているのかいないのか、ただカネを受け取って喜んでいるのです。
現在の駐米日本国大使館はこれに反撃していますが、いかんせん「武器・弾薬」が貰えていません。外務省報償費(俗に言う「外交機密費」)の使い道や、州政府や連邦政府に出入り出来る現地人を工作に雇う方法など、内閣官房に「国民の覚悟と提案」をしましょう。
そのようなことに一円の血税も使って欲しくない、という方は結構です。近い将来、単なる呼称問題が原因で、日本海に於ける海底資源の採掘や漁業などの権利を韓国に奪われ、私たちが大きな損失を被っても致し方ないのでしょう。
海外では、反撃しなければ承諾したものと思われます。ヴァージニアの「フィリップモリス」や、ニューヨークに本社がある「ティファニー」の不買運動もよいかもしれません。
分類:亜州・太平洋関連, 日本関連, 欧州露・南北米関連 | コメント1件 »
皇紀2674年(平成26年)2月11日
本日は、初代神武天皇の御即位日(日本書紀による)から明治六年に定められた紀元節です。天皇弥栄。
——————————
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140208/crm140208……
▲産經新聞:10日にもJR北海道告発 国交省、改ざんで監査妨害の疑い
国土交通省および運輸安全委員会は十日、それぞれ鉄道事業法違反のほか同委員会設置法違反の容疑で、JR北海道を初めて北海道警察に刑事告発しました。
昨年十二月二十五日記事でJR北の問題を取り上げましたが、これは決して私の虚妄の類いを書き連ねたのではありません。警察庁は、平成八年以降の極左団体「革マル派」への捜査で、JR北とJR東日本のJR総連系労働組合への革マル派の浸透は「相当なものだ」と認識しているのです。
警察庁の高橋清孝警備局長は、昨年十一月七日の参議院国土交通委員会でそう答弁しており、現在の状態を「鋭意解明中だ」とも述べています。私はこの時点で、国交省鉄道局が行政指導するだけでは手緩いと考え、刑事告発の可能性について、或る方を通して打診しました。
その際、手応えを感じたがゆえ記事にしたのですが、つまり国交省は、昨年末から刑事告発の可能性を模索していたのです。これを、JR北改組の第一歩にしなければなりません。公共運輸は、人命を乗せて走るのです。
分類:日本関連 | コメント2件 »