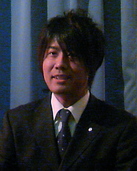皇紀2674年(平成26年)12月16日
http://www.sankei.com/premium/news/141214/prm141214……
▲産經新聞:【お金は知っている】 「円安人民元高」時代 日本企業は中国に見切りを
たいていの選挙事務所は、お年寄りだらけです。長年政権を担当してきた自民党の政治を産む正体は、お年寄りに売り倒してきた「媚」そのものと申して過言ではありません。
その結果、わが国は少子高齢化(老人がなかなか死なない)に至る医療・保険制度を完成させ、「長生きすることはよいことだ」というお題目を一億総国民に唱えさせてきました。
産經新聞社の田村秀男特別記者が指摘するとおり、わが国の内需萎縮は、私も何度も申してきたように、二十九年前の「プラザ合意」から始まっていたのです。そのときからじわじわと、若い労働力(頭数)を必要としない貧しい国家への転落が始まりました。
田村記者の「通貨水準の変更は一国の運命を狂わせる可能性がある」というのは、近隣の韓国と中共を見ても明らかであり、プラザ合意以降の円高で、泡沫経済の崩壊という最大要因もありますが、わが国から製造業が逃げ出していったのです。
それでは雇用そのものがありません。しかし、中小企業の現場では、人手が不足しています。募集をしても、すぐに辞めるような若者しか応募しません。経営者の中には、頭を抱えている人も多いのです。
これも、何だかんだ言って自民党が進めてきた教育行政の賜物でしょう。減反で農家を支えるような農政も、自民党の仕業です。
安倍晋三首相は、これらを大きく変えると言って再登板を許された為政者ではなかったでしょうか。
少子化で老人にも労働を課し続けると言いますが、当選十回以上で議長まで経験した老人が「初心に帰ってがんばります」などと立候補を続けるようなもので、人の一生でなぜ七十歳を超えて初心に帰らなければならないのか、と。衆議院の伊吹文明議長や横路孝弘元議長にはうんざりします。
第三次安倍内閣は、明確に「中共を倒す」日本経済の政策を実行すべきであり、かつて米国がわが国にやったような「えげつない手法」も駆使して勝ちにいかなければなりません。
そのためにも必要なのは「情報」であり、つまるところ軍事技術なのです。占領憲法(日本国憲法)のままでは、それを手にすることはできません。
暮らしと憲法の問題が直結するというのは、そのような意味であり、偉そうな老人や役人が若者たちに向かって「君たちが死にに行って」というような話をすることではないのです。
分類:日本関連 | 「中共を倒す」とすべし はコメントを受け付けていません
皇紀2674年(平成26年)12月15日
http://www.sankei.com/politics/election2014/board/……
▲産經新聞:衆院選2014特集 開票結果
・占領統治以降、過去最低の投票率に終わった第四十七回衆議院議員総選挙。その原因は、デフレーション(給与下落)対策を掲げたはずの安倍晋三首相が思い切った消費税減税(三党合意に基づく法律の破棄)を公約に掲げず、単に「増税を先延ばしする」としか言わなかったことが最大でしょう。
・民主党は、改選前より議席を増やしたにもかかわらず、海江田万里代表(東京一区)を落選させてしまったため、組織としてはありえない姿を露呈させました。東海地方での躍進は、労働組合の引き締めが効いたせいでしょうが、代表を見殺しにした組織に未来はありません。
・海江田代表がまったく党の顔になり得なかった民主党に対し、いわゆる「反与党」の票は日本共産党に流れました。しかしながら、つくづく「消費増税の中止(すなわち八%税率の放置)」としか公約に掲げなかったことが残念です。
・次世代の党は、共産党とともに「どこまで議席を獲得するか」と注目した政党ですが、やはりことのほか経済政策に関する公約に不可解な点があり、実際に(決して私は組織として別働隊を担っていませんが)支持を呼びかけてもよい返事は得られませんでした。国民経済が苦しんでいるときに、憲法問題に加えて外交や安全保障、教育などで立派なことを謳っても理解されません。立派なことを実現させるためにも、デフレの現状を直視すべきではなかったでしょうか。
・結局のところ保守層(いわば「安倍信者」)の支持は「安倍自民党」に偏り、革新層の支持は民主党と共産党で分け合いました。その結果、公明党(創価学会)の議席増をも招き、維新の党が議席を減らし、社会民主党は予定どおり風前の灯と化したのです。
・候補者にもおかしなのはたくさんいましたが、例えば小渕優子前経済産業相(群馬五区)の手を握りながら「世間の荒波に負けないで」などと口走る高齢の有権者にも、失礼ながら大いなる問題はありました。これは私たち自身の問題です。小渕問題は、追及した「世間」が悪いのですか? そのような感覚で投票してしまう私たち国民の意識こそ、最低の投票率で単に与党を圧勝させてしまったことに繋がってはいないでしょうか。
・このままの経済政策では、ほぼ内需回復は見込めません。本日発表の日銀短観では、大企業までもが業績を落とし始めていることが分かっています。よって、次の第二十四回参議院議員選挙で恐らく自民党は大敗するでしょう。それは自民党の勝手ですが、私たちの暮らしはそれでは困るので、私は今後、皆様とともに不断の政策提言で方向性の修正実現を目指します。
分類:日本関連 | コメント2件 »
皇紀2674年(平成26年)12月14日
本日は、衆議院議員総選挙の投開票日であり、最高裁判所裁判官国民審査の日です。期日前投票をされていない有権者の方は、本日必ず投票および審査に行かれてください。
——————————
http://www.sankei.com/world/news/141212/wor141212……
▲産經新聞:【大韓航空騒動】“ナッツ副社長”出頭し、小声で「おわびする」 父親は会見で「しっかり教育できず申し訳ない」
まず、当該大韓航空機は、一体どのような嘘をついて航空管制に引き返しの許可を得たのでしょうか。と申しますのも、通常「客室乗務担当を降ろしたいので引き返す」では、許可されません。
また、大韓航空では、ファーストクラスでナッツを出しているのでしょうか。袋ごとだったか否かより、まずそのことに驚きです。
ソウル市立交響楽団の女性代表といい、自分は偉いと勘違いした者の暴走がことのほか酷いのは、お国柄でしょうか。
——————————
http://www.afpbb.com/articles/-/3033979
▲AFP:グリーンピース、ナスカの地上絵を「破損」 ペルー政府激怒
どの記事にも「国際環境保護団体グリーンピース」とありますが、もう「国際環境破壊団体」でよいと思います。
以前に、沖縄県辺野古沖で「珊瑚を守れ」などと言って過激な活動をしている人たちは、なぜ東京都小笠原諸島沖には行ってくれないか、と指摘したことがありますが、この破壊団体も同じです。
何やら聞こえのよいことをおっしゃるが、「環境保護団体シーシェパード」こと「環境名目のテロリスト集団」の類いと同様に手法や手段が卑劣すぎて、特定国家への攻撃に利用しているに過ぎません。
分類:亜州・太平洋関連, 日本関連, 欧州露・南北米関連 | コメント1件 »
皇紀2674年(平成26年)12月13日
http://www.sankei.com/life/news/141212/lif141212……
▲産經新聞:皇后さま、ベルギーにご到着
第五代ベルギー国王だったボードゥアン一世のファビオラ王妃が五日に亡くなり、国葬ご参列のため、皇后陛下がブリュッセルに行啓されました。
ほぼ「弾丸ツアー」に近いご日程でも、わが国国民とベルギー国民の友好関係のため、そして何よりご交流があったことへのお気持ちを表そうとなされた陛下に、国民の一人として感謝申し上げます。
——————————
複数の方からご指摘いただいたのですが、衆議院議員総選挙の投開票が近づくにつれ、或る種の嫌がらせ工作が散見されるようです。
例えば、まったく私の知らないところで「遠藤健太郎は次世代の党の別働隊」といった事実無根の中傷がありました。
組織の別働隊として、いわゆる「集票マシーン」と化すには、無思考・無批判にして徹底した服従を約束せねばなりません。
しかし、私はすでに次世代の党の公約のうち、経済政策の部分をわざわざ批判材料として取り上げています。このようなことは、別働隊ならば決して許されないことであり、極左系の場合、恐らく一点の批判でも生命まるごと始末されるでしょう。
また、十一日記事のような内容に対しても、信じられないほどつまらない工作を仕掛けてくる人がいるようです。「米国で干ばつなど起きていない」、よって「遠藤の情報は信じてはいけない」というものでした。
これもよく調べていただければ分かりますが、私が畜産との関連で調べた上で「米南西部と西海岸」と指摘した地域の干ばつは、以下のような報道にもなっています。
ロイター通信:本年六月二十二日記事「米国の干ばつ、水をめぐる経済戦争の火種に」より「米カリフォルニア州と米南西部を襲った草木を枯らすような干ばつが」
ナショナル・ジオグラフィック:本年十月号掲載記事「雪不足が招く米国西部の干ばつ」より「米国西部は慢性的な水不足に悩まされている」
ブルームバーグ:本年十一月四日記事「干ばつ悪化の米加州、加工用トマトの生産高が過去最高水準に」より「カリフォルニア州では3年間にわたって降水量が過去最低水準にとどまり、82%が極度の干ばつに」
本当にうんざりします。
分類:日本関連, 欧州露・南北米関連 | コメント3件 »
皇紀2674年(平成26年)12月12日
http://www.nikkei.com/article/DGXZZO75366460X00……
▲日本經濟新聞:もう一つの投票 備えておこう「最高裁国民審査」
衆議院議員総選挙と同時に投票するのが、最高裁判所裁判官の国民審査です。現行制度には問題も多く、周知が不徹底で、且つ概して私たちの分かりにくい事柄であるため、審査結果が実際に反映されたことは一度もありません。
しかし、ここでも何度か取り上げてきたように、最高裁決定または判決がどう考えてもおかしな場合はいくつかあり、私たち一般の感覚を取り入れるためにと始まった裁判員制度ですら正しく機能しているとは思えないのです。
そこで、今回審査対象の五名について、選挙管理委員会による最高裁裁判官国民審査公報を参考に、注目すべき実績を取り上げます。あえて論評はしません。皆さんのお役に立ちますように。
■鬼丸かおる 昭和二十四年二月東京都生まれ。東大法学部卒。
平成二十五年九月四日 大法廷決定
婚外子(非嫡出子)の相続分を嫡出子の二分の一と決めた民法九百条四号但し書前段の規定は、憲法違反である。(全員一致)
※ 同年九月六日 いわゆる東京「君が代」判決 不起立教員について「命令不服従に対する不利益処分は、慎重な衡量的配慮が求められるというべきである」との補足意見を述べる。
■木内道祥 昭和二十三年一月徳島県生まれ。東大法学部卒。
平成二十五年九月四日 大法廷決定
婚外子(非嫡出子)の相続分を嫡出子の二分の一と決めた民法九百条四号但し書前段の規定は、憲法違反である。(全員一致)
※ 学生運動への参加経験があるとの情報あり。
■池上政幸 昭和二十六年八月宮城県生まれ。東北大法学部卒。
平成二十六年十一月十八日 第一小法廷決定
公判審理を担当している裁判所が、被告人の保釈を許可したことに対し、抗告を受けた裁判所として、被告人が罪証隠滅行為に及ぶ可能性は低く、保釈の不合理を示せない限り、これを許さないとした抗告審の決定を取り消し、改めて保釈を許した。(全員一致)
※ 検察庁検事の出身。
■山本庸幸 昭和二十四年九月福井県生まれ。京大法学部卒。
平成二十六年六月十三日 第二小法廷判決
当時の厚生労働行政に不満などを募らせたからといって、元厚労事務次官とその妻を数回にわたって刃物で刺し、殺害したことなどについて、死刑の科刑はやむをえない。(裁判長として 全員一致)
※ 記者会見で「集団的自衛権の行使は、従来の憲法解釈では容認は難しい。実現するには憲法改正が適切だろうが、それは国民と国会の判断だ」との発言あり。
■山崎敏充 昭和二十四年八月大阪府生まれ。東大法学部卒。
平成二十六年十月二十八日 第三小法廷判決
違法な無限連鎖講(いわゆるネズミ講)で破綻した会社の破産管財人が、清算の過程で、配当を受けていた会員から配当金の返還を求めたのに対し、配当が不法原因給付に当たることを理由として返還を拒むことは、信義則上許されない。(全員一致)
※ 東京高裁長官時代、江東区竪川公園の不法占拠に端を発した極左の破壊活動に対し、厳しい審判を下した判決を見守った。
※ 十二月九日 第三小法廷判決(裁判長として) いわゆるヘイトスピーチを行ったとされる団体の上告を退けた。
分類:日本関連 | 最高裁判事国民審査の資料 はコメントを受け付けていません