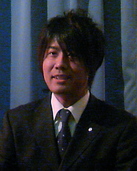皇紀2682年(令和4年)8月27日
大阪府高槻市の資産家女性を保険金目的で殺害したとされる髙井凜容疑者(旧姓=松田)が逮捕直前まで住んでいたいわゆる「タワマン」は、衆議院赤坂議員宿舎裏の「赤坂タワーレジデンス Top of the Hill」だそうです。よほど浮かれて住んでみたのでしょう。
保険金殺人の量刑は大抵、最高裁判所まで争っても無期懲役を免れません。人を騙して殺めた上に成り立った暮らしは、恐らくこれから死ぬまで続く償いの日日によって、すべて幻だったと思い知ることになるでしょう。
さて、二十五日記事で「ともすれば日本テレビと讀賣新聞社は、特に統一教会との関係をきつく暴露されて終了するかも」と申したことが早速、始まりました。
ほらね。日テレは、放送直前の「二十四時間テレビ」を統一教会(世界平和統一家庭連合)に狙い撃ちされました。系列局の統一教会信者スタッフが七年間にわたって番組に関わり続け、エンディングではご丁寧に「七尾市/世界基督教統一神霊協会能登教会」のクレジットまで放送されていたのです。
同じく別の系列局制作の情報番組が統一教会関連報道を続けていますが、ここもいつ関係が暴かれるでしょうか。日テレ本体共ども、ないと思ったら大間違いです。
因みに、近ぢかテレビ朝日も危ないですよ。また、日テレは、今回の暴露が「ほんの序章」に過ぎないことを覚悟しておきましょう。まず「あれ? 話はこれだけ?」と思いましたから。
統一教会の「韓国本店」が焦って復讐に打って出たせいもありますが、私にいわせれば、統一教会自体の問題ではなく利用された自民党議員に対する追及ばかりしているうちに、報道権力自身が墓穴を掘った顛末です。
政治家は、近寄ってきた「親切な支持者たち」を袖には出来ません。選挙の時には、大いに頼りにしてしまいますし、それが「民主主義」のしんどいところでもあります。
統一教会に利用され、政治家も彼らを利用してきた側面はありますが、問題の本質が統一教会の存在そのものにあることを忘れてはいけません。
こうした暴露攻撃に縮み上がるのではなく、統一教会のみならず創価学会も批判の対象とし、徹底して報じることで公明党を政権から叩き出し、わが国版「反セクト法」と「スパイ防止法」の成立に向けた世論喚起に努めることです。
それしか報道権力の生き残る道はありません。スパイ防止法には反対したいでしょうが、統一教会も創価学会もこれなくして組織壊滅へ追いやることなどできないのです。
自民党議員には容赦なかった「知らなかったんですぅ」と自らもいいつつ、腹の内では「よくもやりやがったな」と思うなら、覚悟を決めて詐欺カルトたちを叩け。
分類:亜州・太平洋関連, 日本関連 | コメント1件 »
皇紀2682年(令和4年)8月26日
岸田文雄首相が次世代型原子力発電所の建設を政府方針として固めました。少しずつではありますが、岸田首相曰くの「聞く力」を発揮し始めています。
東日本大震災による東京電力福島第一原発事故で、私たち国民は、改めて日米原子力協定以来の米国製軽水炉型原発では「駄目なんだ」と思い知りました。
現行憲法(占領憲法)にどっぷり浸かり、ぼんやりしていた私たちがいけなかったのです。事故が起きてから目が覚めたのでは、私も含めて情けない限りでした。
軽水炉型の中身は、いわば「ブラックボックス」状態で、まして災害列島のわが国で一度事故が起きればどうにもならない代物だったのに、まるで気にもかけずにその恩恵を受け続けてきたのです。先進国の最低条件は、電力の安定供給ですから、それなくしてわが国の経済発展はありませんでした。
だからこそわが国の三菱重工業らが開発してきた次世代型原発は、まずわが国で採用、新設されるべきだと訴えてきたのですが、その間にも諸外国には輸出されています。
岸田首相が「脱炭素」に絡めて発表したのは気に入りませんし、それをいうなら現行わが国の燃料混合型火力発電所は、既にほぼ二酸化炭素を排出しません。何となくの印象だけで火力発電を「悪者」扱いしてはならず、原発だけが脱炭素目標を達成する発電方法ではないのです。
日本の技術力を舐めてはいけません。
そもそも「脱炭素」に目の色を変える必要などどこにもありませんが。
武漢ウイルス(新型コロナウイルス)対応にしても、二年以上にわたる莫迦騒ぎを鎮めねばならない今、いわゆる「全数把握」をやめると示したにもかかわらず、肝心のところを莫迦揃いの地方自治体首長任せにしたため、早速東京都の小池百合子知事や大阪府の吉村洋文知事が武漢狂乱を続ける意向を発表し、台無しにしてしまいました。
知力下層の莫迦知事たちを黙らせるような迫力が、まだ岸田首相にはないのです。
菅前首相、選択的夫婦別姓に前向き姿勢

菅義偉前首相は23日、角川ドワンゴ学園が運営する通信制高校の生徒を対象に行った講義で、選択的夫婦別姓制度について「これ以上先送りしないで、政治の責任で議論して…
(産經新聞社)
それも何もかも菅義偉前首相が武漢狂乱利権を定着させてしまったことに起因します。岸田首相は現職として、この「壮大な汚職」をやめさせる必要があるのです。
その菅前首相は、安倍晋三元首相を支え続けた内閣官房長官時代以来、封印してきた選択的夫婦別姓(別氏)制度の推進を、どうやら諦めていませんでした。安倍元首相が暗殺されてしまい、止める者がいなくなってしまったせいもあるでしょう。
この制度は、決して「国民の自由」ではありません。「選択的」だから「個人の勝手」では済まない大問題を抱えた制度であることを、何としても周知していただきたいのです。
直近では六月十四日記事で扱いましたので、改めてお目通し願います。夫婦別氏が基本的女性差別主義であるのみならず、子供の人権にも大いに影響を及ぼしており、別氏制度を導入した国ぐにの失政が明るみになってきました。
このようなものを今さら導入しようとするわが国の政治家は、いつも「周回遅れ」なのです。絶対に阻止しましょう。
分類:日本関連 | コメント3件 »
皇紀2682年(令和4年)8月25日
報道権力が統一教会(世界平和統一家庭連合)問題を自民党批判にすり替えているうちに、自分たちが統一教会との関係を暴露されそうになっている今、実は立憲民主党どころではない全野党との関係があからさまになりました。
目下の報道権力が基準としている「統一教会との関係」でいきますと、世界日報社の出版物に名を連ねただけで攻撃の対象になりますから、ならば『日本が動く時 政界キーパーソンに聞く15年』の中に立民の枝野幸男前代表、岡田克也元外相(それでも次期幹事長内定か)、小沢一郎衆議院議員のほか、何と社民党の福島瑞穂参議院議員、日本共産党の志位和夫委員長までもが登場しています。
これは、長野祐也元衆議院議員(故人)のラジオ日本系番組放送開始十五周年記念の本ですが、ともすれば日本テレビと讀賣新聞社は、特に統一教会との関係をきつく暴露されて終了するかもしれません。いや、フジテレビ系列も放送局生命の死から決して逃れられませんが。
こうなりますと、まさに墓穴を掘ったようなもので、安倍晋三元首相の暗殺が「自業自得」「因果応報」であるかに扱った自分たちの行ないこそがそれでした。
とにかく「群がられる」政治家に統一教会が接近(利用)していったことを、統一教会側の問題ではなく自民党議員側の問題とした報道権力は、ならばアレもコレも駄目ということになりますが、本当によいのですね?
私が一貫して何年も申し続けてきた「反共の皮を被ったただの詐欺カルト」という正体は、共産党委員長までもを使ったことで分かる、ということでよろしいですね?
報道権力の皆さん、これから地獄の門が開きます。知りませんよ。
しかしながら読者ご指摘の通り、これで「日韓トンネル」なるものがいかに「トンデモ」な代物か、広く国民に周知されてよかったとも考えられます。
もう一つ、報道権力が血道を上げて応援したウクライナですが、反露を叫んで北大西洋条約機構(NATO)入りを「英断」と讃えたフィンランドのサンナ・マリン首相に醜聞が持ち上がり、それが一斉に報じられました。
わずか三十六歳の首相が休日に、その重責を逃れて友人たちと「パリピ」になるのは、仕方のないことでしょう。問題は、その様をあれほどはっきりと動画に撮られていたことです。
恐らく露国の連邦保安庁(FSB)の諜報員がマリン首相の真横で堂堂と撮っていたと思われます。さらに問題なのは、それに全く気がつかないマリン首相の間抜けぶりと、フィンランドに諜報能力が全くないことです。
最近「凋落した」などと揶揄されてきたFSBですが、駄目な国を狙うのは、いとも簡単でしょう。フィンランドは、まんまとやられたのです。
ということは、わが国も当然、諜報工作の容易な国に該当します。延延申しますが、スパイ防止法のないわが国は、駄目な国なのです。
これに反対する報道権力は、すなわち(安倍氏訪台阻止の指令に従ったともされる)中朝の工作員を多数抱える組織ということでよろしいですね?
本日記事は、一体誰に向けて申しているのでしょう。気分を害した記者がいたらごめんなさい。
分類:亜州・太平洋関連, 日本関連, 欧州露・南北米関連 | コメント1件 »
皇紀2682年(令和4年)8月24日
暗殺された安倍晋三元首相の国葬儀に対し、未だ「法的根拠がない」などと叫び続ける危険な活動家たちは、内閣府設置法第二章第四条第三項の三十三が読めない人たちです。
つまり、国葬儀反対署名の活動を始めたらしい東京大学の上野千鶴子名誉?教授らは、自身で「私は阿呆です」といっているようなもので、つくづく「可哀想(笑笑)」な連中でしかありません。
しかし、もう「こんな人たち」のために国葬儀が執り行われるのではないのです。暗殺後から外務省に問い合わせが殺到したように、安倍元首相を悼む海外要人(大統領や首相ら)が参列するために執り行われます。
移民という言葉を避けながらの移民推進策を含む経済政策にも、日露外交にも失敗した安倍元首相でしたが、そのあまりに尊い犠牲は、他に代え難い外交的価値を発揮しました。
それは、私たち国民だけがわが国報道権力によって知らされなかった「リベラル派宰相・安倍晋三」が世界各国から高い評価を浴び続けたからで、安倍元首相をこれまた未だに「右翼政治家のアベを死んでも許さない」などとわめいている人たちは、国際政治の流れも何もかも分かっていない莫迦です。
そのことは、安倍元首相の在任期間中にも指摘しました。私が特に仏独の報道に驚かされたのがきっかけです。
外務省は来月二十七日の国葬儀に向け、既に六千四百人規模の招待状の準備に入りました。かねがね葬儀参列を希望していた要人たちを数え、確実に六千人を超えたためです。
国葬儀にかかる費用をいう「さもしい」阿呆莫迦は、消費税法の無効(消費税廃止)と所得税控除額の引き上げなどにもっと、真剣に声を上げてもらえませんか。そういう声に限って極めて小さく、阿呆莫迦案件だけ喚きちらすのは、私たち国民の迷惑です。
旧統一教会と関わり、枝野氏・安住氏ら立民6人判明…泉代表「ごまかそうとしているのが自民」

立憲民主党は23日、「世界平和統一家庭連合」(旧統一教会)と関わりがあった党所属国会議員について、枝野幸男・前代表や安住淳・元財務相ら新たに6人が判明したと発表した。関連が明らかになった立民の国会議員は計14人になった…
(讀賣新聞社)
なぜなら「こんな人たち」を応援する人たちだからでしょう。程度が知れていますし、お里も知れます。
統一教会(世界平和統一家庭連合)問題で私は、常に「立憲民主党もまみれている」と指摘してきましたが、やはりその通りでした。自民党批判にすり替えて話を逸らす報道権力は、統一教会に「関係」を暴露されればよいのです。
何が「誤魔化そうとしているのが自民党の姿勢」ですか。正しくは「自民党批判に隠れて誤魔化せると思い込んできたのが立憲民主党の姿勢」です。
署名活動には、岸信夫前防衛相の偽投稿(フェイク・ツイート)を拡散した犯人の一人である高千穂大学の五野井郁夫教授?もおり、本当にわが国大学教育の致命的劣化を伺い知れます。
政治家も学者も、もはやそう呼称できない低次元な「ただの阿呆」でしかない者ばかりです。私たちにできることは、このような阿呆莫迦の腐った言動に決して引きずられないことです。
分類:亜州・太平洋関連, 日本関連 | コメント1件 »
皇紀2682年(令和4年)8月23日
現下の報道権力が統一教会(世界平和統一家庭連合)そのものをまともに批判できず、自民党批判にのみ血道を上げ話を逸らし続けているのは、ただ自民党批判が「生き甲斐」だからのみならず、統一教会らとの関係が自分たちにも及んでいたことの発覚を恐れているからだと申しましたが、やはりそこを統一教会に突かれてしまいました。
統一教会が報道各社に出した「異常な過熱報道に対する注意喚起」には、「各報道機関と当法人および友好団体等とのこれまでの関わり等について、過去に遡って詳細な調査を進めております。調査結果がまとまり次第、全面的に公表させていただく予定です」などと書かれています。
お分かりでしょう。いざとなればこうして政治家も脅してきました。自分たちとの関係を「醜聞」扱いできるのは、自分たちが腐った詐欺カルトでしかない自覚があるからです。
このような組織に支援されれば、必ずいつか痛い目に遭います。だからこそ「装われた反共」以来の縁を切って、統一教会をわが国から叩き出さねばならないのです。
立憲民主党議員も「まみれて」いるのに、自民党議員だけを叩いてやり過ごそうとした報道権力は、なぜ自民党議員たちの歯切れが悪かったのか、自ら思い知ることになるでしょう。
FUKUDA MAKOTO 【DOJNo.0001】 @8ueBd6tf29iYRpZ
#スパイ防止法の制定を #DOJ
小野田議員「私たち政治家は、国民の皆様の代わりに剣となり盾となり皆様の命、財産、平和と暮らしを護るのが仕事!もう一つ掲げているものがスパイ防止法です!これは絶対やらなきゃいけない!スパイ防止法に反対するはスパイじゃないですか!と私は思う!」
(Twitter)
さて、最近では七月三十日記事で言及したいわゆる「スパイ防止法」について、SNS上の議論が再燃しています。きっかけは、高市早苗内閣府特命(経済安全保障)担当相の就任です。
首相官邸に木原誠二内閣官房副長官のような「有害無能」な経済政策の司令塔が存する限り、高市担当相は動きづらいに違いないのですが、それでもスパイ防止法制定の議論を喚起する、してくれると私は思っています。
霞が関省庁がこれに後ろ向きだったのは、法案名によるところが大きく、その仰仰しさが国民的反発を招くと考えられてきましたが、過日の記事でも申しましたように、私たち国民の暮らしのすぐそこまで露中朝らの工作員が迫ってきました。
警視庁が企業に異例の警告を発さねばならないほど事態は深刻であり、スパイ防止法なきわが国をこのままにしては、私たち国民が次つぎと工作員の餌食になり、何らかの刑罰を科せられてしまいます。
本当にわが国の国会議員なら、この事態を打開してくれなければなりません。
ところが、社民党の福島瑞穂参議院議員や、れいわ新選組の山本太郎代表らは、こぞってこれに強く反対する意見を表明し、高市氏批判を展開しています。
私たち国民の生活危機になどお構いなしです。
山本氏に至っては「政権に批判的人物を工作員に仕立て上げるから」などと中共まがいの屁理屈を述べていますが、仮にもそう思うなら、そうならないよう法案審議を尽くすのが議員の務めでしょう。
さすがは国会内でわめくだけで議員立法一つ出したことのない政党らしく、まともな議論から常に逃げてきたのは、自民党よりれいわ新選組のほうです。
二十日記事でも改めた韓国軍による火器管制レーダー照射問題の根っこに北朝鮮の「瀬取り」を隠蔽しようとした文在寅政権の謀略があったように、彼らはこの法案の成立によって、わが国で暗躍する中朝の日本略奪(侵略)工作が明るみにされてしまうのを恐れています。
小野田紀美防衛政務官の指摘通り、スパイ防止法に反対する人は、自分が中朝の工作員だからではありませんか?
法案名は何でも結構です。とにかくスパイ防止法相当の法案作成を急ぎ、その一刻も早い成立を求めましょう。
分類:亜州・太平洋関連, 日本関連 | コメント1件 »