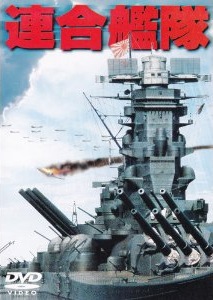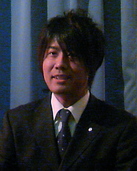もはや世の中、荒みきり…
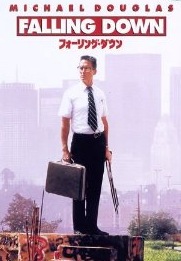 先日、或る方から伺ったお話に、私はすっかり呆れてしまいました。警察が交通違反を取り締まるなどの際に、ここ数日で一気に増えたのが違反者からの抗議なのだそうです。彼らの共通した言い分は「中国人が海上保安庁の巡視船にぶつけて謝りもせず無罪放免なら、こうして謝っている日本人の私のこんな違反ぐらいで罰金または減点に処さないで欲しい!」というものなのだとか。これでは現場の警察官が気の毒です。
先日、或る方から伺ったお話に、私はすっかり呆れてしまいました。警察が交通違反を取り締まるなどの際に、ここ数日で一気に増えたのが違反者からの抗議なのだそうです。彼らの共通した言い分は「中国人が海上保安庁の巡視船にぶつけて謝りもせず無罪放免なら、こうして謝っている日本人の私のこんな違反ぐらいで罰金または減点に処さないで欲しい!」というものなのだとか。これでは現場の警察官が気の毒です。
実は私自身も、滅多に乗らない電車の中で驚くべき体験をしています。携帯電話で通話しつつ乗車してきた会社員らしき男性に向かって、背広に身を包んで読書をしておられた初老の紳士がいきなり怒鳴り始めたのです。当然携帯電話の使用に係る社会規範と礼儀のなさを説かれたわけですが、噴き出す怒りを抑えられないのか「これだから民主党政権ではダメなんだ! 今の政治は皆が勝手なことばかりしても構わない世の中にしている」と、にわか車中演説が止まりません。
また、仕事で招かれて乗せていただいたタクシーの運転手からも民主党政権に対する致命的な非難の声を、往復のまったく別のお2人から聞かされてしまいました。往路でやはり「社会規範の崩壊を食い止める能力は今の政治にもうない」と、復路では「これほど弱い外交で国内景気などよくなるわけがないことを思い知った」というご意見です。
いずれも別段民主党と国民新党の責任だけではなく、創価学会が国家権力の座に就いた公明党と自民党の連立政権以来、いえ素人集団の細川非自民・非共産連立政権を許した頃、もっと申せば昭和30年に始まった「改憲・保守・安保」と「護憲・革新・反安保」という不毛な対立ごっこを始めたときから日本の病気は静かに進行してきたと言えましょう。病名は「GHQ型占領憲法依存症」です。
しかし、いよいよ世の中がこうも荒み始めたかと気掛かりでなりません。人々の不満と憎悪の物理量が蓄積されてくると、決して国家国民にとってよいことは起きないでしょう。それをどうにかせねばならぬ責任は、確かに現在の菅政権にあるのですが……。
こうした世の中の如何ともし難い不満や沈滞感を描いた作品としてまず思い出すのが、平成9年製作・公開の米国映画『フォーリング・ダウン』(『オペラ座の怪人』などのジョエル・シューマッカー監督作品)です。
或る中年男性(マイケル・ダグラス)は、極めて些細なことをきっかけに国家社会への怒りを爆発させていきます。それは、決して観客の同意・同情を得る表現になってはいません。そこが興味深い展開であり、例えば韓国人経営の商店を襲撃するに至るは、ほとんど言い掛かりに過ぎないと観る者に思わせます。
ところが、月並みな評論でお許し願うなら、本作の下敷きになっているのは前年に起きたロス・アンジェルス暴動であり、主人公が失業していることも然り、韓国人の異常な黒人差別からくる黒人少女射殺事件の発生を基にした前述の描写へと繋がるのです。
日本では特に在日韓国人への「やさしい配慮」からか、主としてロドニー・キング事件が暴動の発端だったと報じられた記憶しかありませんが、実は既に平成元年製作・翌年日本公開の『ドゥ・ザ・ライト・シング』(『マルコムX』などのスパイク・リー監督作品)が描いていたように、非常に長い年月をかけて重層的な怒りが人々を、街を包み込んでいたことが暴動の引き金となりました。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101118/crm1011180131004-n1.htm
▲産經新聞:民主・松崎議員が自衛官を「恫喝」か 「俺を誰だと思っている」
この事件なども大いにその引き金になりうるものであり、或いはもう引き金を引いてしまったあとかもしれません。民主党の松崎哲久衆議院議員(埼玉10区)が航空自衛隊員に「俺を誰だと思ってるんだ」などと恫喝し、「やれば出来るじゃないか」などと人を莫迦にし、挙げ句に隊員が我慢ならずに「2度と来るな」とつぶやいてしまい、それを松崎代議士に聞かれて胸ぐらを掴まれています。
よく記事をご確認いただくと、この事件の後にそもそも民主党を「要らない」と挨拶したのは元自衛官とはいえ民間人であり、それでも昨日記事でお伝えしたような言論統制に向けた通達を政府がやってしまったのです。或る種嘲笑気味に申せば、自公連立政権は現職の航空幕僚長に対する言論統制はやりました。
現下の日本列島を支配するのは、この負の物理量です。もはや危険水域に達すると爆発するかもしれません。
中国の尖閣侵略糾弾 全国国民統一行動 11.20 IN 大阪
「頑張れ日本!全国行動委員会」からのお知らせです。
http://knnjapan.exblog.jp/12210963/
※ 当初の街頭演説場所が変更になりましたので、ご注意下さい。
↓↓↓クリックして下さい!
政治部門・映画部門の2カテゴリー登録になっています。ご了承の上、何卒ご協力下さい。
↓↓↓こちらもクリックして下さい!
▼北方領土の哀しい歴史を忘れるな!