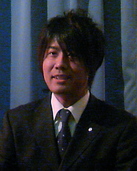産經新聞社と民主党
 産經新聞社記者の方への連絡板がわりに書くのも恐縮ですが、これはどうなっているのですか?
産經新聞社記者の方への連絡板がわりに書くのも恐縮ですが、これはどうなっているのですか?
http://d.hatena.ne.jp/sankeiaidokusya/20101010/p1
▲産經新聞愛読者倶楽部:産経労組が連合に加盟…つまり民主党支持
とうとう産経グループ労組連合会がUIゼンセン同盟に加盟したそうです。ご承知の通り、彼らは民主党最大の支持母体である連合の傘下であり、自治労や日教組の同類と申して過言ではなく、これで民主党や日教組がまともだったらよかったのですが、そうでない現実をどう批判するのでしょうか?
誰が何と言おうと、旧民社党系でまともなのは西村眞悟元防衛政務次官だけです。
「反民主・反日教組の産經」と言われていながらも、致命的な批判は絶対にしないのでしょう。そもそも現存メディアに期待すること自体が間違いなのですが、ブログ『産經新聞愛読者倶楽部』の方も指摘されているように、周囲にも産經新聞記事のおかしさが露呈し始めたのは、確かにこの3年くらいで顕著でした。
国を守るために国家権力の間違いに斬り込んでいくことを「権力監視」と言うのであって、日本のメディア各社は日本そのものを否定しまくっています。その顔色を伺って立ち回り、占領憲法官僚に言いくるめられてきたのが日本の政治家たちでしょう。
産經新聞社のみならず、朝日新聞社の中にもこれが分かる記者の方はおられ、私が主張しているようなことに支持の意を強く示して下さるのですが、朝日は書かせてももらえず、産經は一旦記事にしてくれるものの、実はまったく別の力が働くのか、のちのち非常に冷たいのです。社の実態に失意し、支局長まで昇られた或る記者の方がお辞めになったこともありましたよね、産經さん。私はがっかりしました。
あくまでズル賢いの(または某国や某カルトの派遣工作員)はともかく、外野に何を言われようとも家族を守るために職を辞すことの出来ない記者は、もう辞したいと願えば願うほど、とても苦しい環境でお仕事をされていると思います。善良なる産經新聞社記者の各位にお願いしたいのですが、中共や某○団ともお親しいらしい住田良能社長の正体および社員の組合活動実態を調べて下さい。
社内報でこっそり書くのはいけません。
↓↓↓クリックして下さい!
政治部門・映画部門の2カテゴリー登録になっています。ご了承の上、何卒ご協力下さい。
↓↓↓こちらもクリックして下さい!