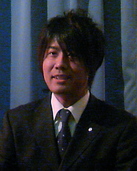NYタイムズは工作新聞?
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110128/amr11012818280042-n1.htm
▲産經新聞:NYタイムズ紙、またも尖閣問題は「中国の主張に理」 日本総領事館が抗議
ザ・ニュー・ヨーク・タイムズ(以下 NYT)はいわゆる「地方紙」ですから、これが米国の世論であるとか、或いは約3億人に達した米国民の認識に大きな影響を与えるものとも言えませんが、この種の情報戦にわが国が無知・無気力であってはなりません。
NYTの対日非難記事といえば「大西哲光(ノリミツ・オオニシ)」を名乗る記者による署名記事が有名ですが、日本の漢字・仮名文化を批判的用法としての「島国根性」に関連づけたり、北朝鮮による日本人拉致事件の解決を阻害するような珍妙なものばかりです。この際には、当時の中山恭子首相補佐官(現在 たちあがれ日本参議院幹事長代理)が反論文を同紙とほか1紙に掲載させました。
今回の一連の沖縄県石垣市尖閣諸島に関する「中共に分がある」「中共に揺るぎない歴史的根拠がある」などの「ならばその国際法上揺るぎない歴史的根拠を法理原則に従って示しなさい」と反論されるべき記事を書いたのは、ニコラス・クリストフ氏です。
東欧系米国人の彼は、2度に渡ってピューリッツァー賞を受賞した記者であり、米国内に於いてはそれが優れた記者であることをほぼ意味しますが、最初の受賞は、中共系米国人の投資家で彼の妻であるシェリル・ウーダンさんとともに書いた天安門事件に関する記事でした。
彼らの生活環境と出自が、昨年9月の記事を巡って在ニュー・ヨーク日本国総領事館の反論を受け取りながらも、本年1月にまたも根拠希薄なまま同じ主張を繰り返した所以なのかどうか分かりませんが、これほど何らの説明もなしに中共の主張だけを繰り返し書く意図は一体何なのでしょうか。
概してGHQ占領統治期以降の日本国民が米国発信の主張に弱いことを知っていて、米国内向けではなく対日情報戦として仕掛けているのか、ありもしない領土問題まで持ち出して日本を弱体化させる工作が既に米国内で進んでいることを意味しているのかもしれません。
このような工作員は、弱々しい日本政府を頼ることが出来ずに決死の覚悟で自ら領土保全に動き出した石垣市民の選択を、取るに足らないものと考えているでしょうし、それほど血も涙もなければ工作員など務まらないものです。
まさか私たちまでもが、平和を乱すような血も涙もない情報工作に同意することはありませんが、毅然と抗議した総領事館の仕事に礼を記しつつも、ならばこれまでの政府対応はどうであったかという問題を提起せざるをえません。わが国政府とて、国際社会の約束ごとに従って必ずしも誠実であり続けてきたわけではないのです。
その一端が、露国による北海道の北方領土実効支配、または韓国による島根県隠岐郡隠岐の島町竹島への武力侵略を許したままにしている現状に表れており、挙げ句には、中共人の魚釣島不法侵入と公共物損壊事件、漁船による当て逃げ事件のそれぞれを、自公連立政権も民国連立政権もうやむやにしてしまったのですから、もう既に私たちの政府は或る種の情報戦に敗れています。
NYTのこれほど莫迦げた工作活動を許しているのは、わが国が米軍による占領統治を終えてなお占領憲法をそのままにしているからであり、例えば大西氏が護憲を擁護しながらも、その実その主張は護憲の現実を利用・嘲笑する米国政府の上に成り立っていることこそ、私たち日本民族が知らねばならないことなのです。
統一地方選直前!2・13「日本よ、たちあがれ!」第二回決起集会
http://www.shinhoshu.com/2011/01/post-173.html
▲詳細は上記リンク記事をご参照下さい。皆様のご参加をお待ちしています。