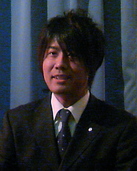皇紀2673年(平成25年)10月25日
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131016/plc131016……
▲産經新聞:元慰安婦報告書、ずさん調査浮き彫り 慰安所ない場所で「働いた」など証言曖昧 河野談話の根拠崩れる
http://www.j-cast.com/2013/10/18186651.html
▲J-CAST:今度はシリコンバレーで「慰安婦問題調査」決議 慰安婦像建立のうわさは否定
きっかけは、大阪市の橋下徹市長(日本維新の会共同代表)が、あたかも俗に「従軍慰安婦」と呼ばれる制度がかつてのわが国にあったかのように肯定し、その時点での必要性に言及した発言でした。
西村眞悟元防衛政務官は、日米豪などで社会問題化している韓国人女性の違法な売春行為について代議士会で指摘し、日本維新の会を追い出されてしまいましたが、事実を言って何ら外交問題にもならなかった一方、同党の橋下市長の発言は内容に著しい間違いがあり、大いに外交問題化しています。もはや「第二の河野談話」と申して過言ではありません。
いわゆる「昭和三十年(五十五年)体制」を崩壊させた宮澤内閣の河野洋平官房長官が平成五年八月、韓国人「従軍」慰安婦の存在を取り上げて謝罪してしまった談話の出鱈目は、これまで多くの有識者が指摘しながら、政府は談話発表の根拠とした調査報告なるものを「特定秘密」のように隠蔽し続けてきました。産經新聞社はその調査報告書を入手し、記事にしています。
そして、亜州系の人口が半数を超える米カリフォルニア州サンタ・クララ郡ミルピタス市の市議会が本年八月六日、米政府に慰安婦問題に関する調査を依頼する決議を採択しました。決議内容について、市民への意見聴取もなければ議員による採決すらなく、ホセ・エステベス市長が署名して韓国の安豪栄駐米大使とその場で記念撮影に収まっています。
これに対しては、姉妹都市提携をしている茨城県つくば市が既に市長の見解を問う信書を送り、「単に調査を依頼するものでしかないこと」「『慰安婦像』なるものを市内に設置する予定はないこと」などを確認して、さらに冷静な対応を求めました。
同州ロス・アンジェルス郡グレンデール市に対して大阪府東大阪市が再三抗議したことといい、地方自治体の姉妹都市提携事業が外交の役に立ちましたが、慰安婦像の設置後に就任したデイヴ・ウィーヴァー市長が「設置は失敗だった」と明言し、ミルピタス市議会にも姿を現した「米州韓人会総連合会」のような在米韓国人からの組織的圧力があったことをほのめかしています。
しかし何度も申しますが、その背景には「世界抗日戦争史実維護連合会」のような在米中共系の圧力団体が強い影響力を行使しており、同州選出のマイク・ホンダ下院議員や、州内各地の首長を中共系に置き換え始めた資金源と申してよいでしょう。
米政府は中共を安全保障上の脅威と捉えながらも、その資金が一部政府機関にまで入り込んでいることから、なかなか「日本の味方」をし切れません。
韓国が事実上、米国を裏切って中共へ寄ったことに米政府も気づいた(チャック・ヘーゲル国防長官の訪韓時にはっきりした)ため、もはや彼らも韓国のために日本へ圧力をかけることはしませんが、世に言う「歴史認識問題」を操るのが中共となれば、米国は自身の利益のためにもわが国の求めには応じないでしょう。
それでも私たちはこの調査決議を、超えられない逆境ではなく好機と捉え、このほど明らかになった政府による出鱈目な調査報告書を、むしろそのまま米政府にも提供すればよいのです。また、私たちはそれを求めましょう。
さらに、皆様にお願いがございます。米国で「Comfort Women Fabrication(慰安婦の捏造)」と題する論文の掲載があり、その拡散を止めるよう米政府に求める請願の署名が始まっていますので、どうか皆様もご協力ください。
http://petitions.moveon.org/sign/comfort-women-fabrication……
▲署名は「Sign this petition」の項目に必要事項を記載し「Sign the petition!」をクリックするだけです。
【11.4 第9回憲法問題決起集会のお知らせ】
詳しくは真正保守政策研究所 公式ウェブサイトをご覧ください。
分類:亜州・太平洋関連, 日本関連, 欧州露・南北米関連 | コメント6件 »
皇紀2673年(平成25年)10月24日
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/131023/wlf131023……
▲産經新聞:「韓国は戦争状態」「反日心配」滋賀県立高の韓国修学旅行に保護者「反対」、実施方針の学校側と対立
滋賀県栗東市にある県立国際情報高校で、十一月に予定する韓国への修学旅行を巡って、保護者の一部から反対の声が上がっており、他の行き先の希望調査すら拒む学校側との対立を深めています。
反対する保護者が心配しているのは、韓国が島根県隠岐郡隠岐の島町竹島を違法に武装占拠しているにもかかわらず歴史認識を盛り込んで「反日」を煽っており、北朝鮮による延坪島砲撃事件(平成二十二年)などからも朝鮮戦争が終わっていない現実を思い知らされたからで、極めて現実的な危険に対するものです。
また、食品への汚物混入や、食堂で先客の食べ残しを使いまわすなどの問題、連合国(俗称=国際連合)麻薬犯罪事務所(UNODC)が韓国の十万人あたりの強姦件数を十三.三件(日本の約九倍)と公表した問題が浮上していることから、旅行中の食事や特に女子生徒の安全を心配する保護者もいたといいます。
私は九月十五日記事で、日韓併合時代を「よかった」と述べただけの老人が若者に殺され、日本人と話していただけの者が日本人もろとも殴られるという事件の発生は、私たちが韓国への渡航を思いとどまるに十分な懸念だと申しました。
しかし、学校側が説明会で言い訳に使った外務省の渡航情報は、このような次元で発せられるものではありません。外務省が「『今すぐに危険はない』と説明している」からといって、当該国が安全だと保証するものではないのです。
まして大人がいわば「勝手に」渡航するならともかく、教員は生徒に対する安全の責任がありますから、現下の韓国に不穏な空気を感じる保護者が反対するのも無理はありません。敢えて生徒を韓国に連れて行き、危険な目にあわせて学習させればよいなどというわけにはいかないでしょう。
これは「何かと学校に依存して因縁をつけたがる保護者」の問題ではなく、学校側が既に旅行代理店と契約したことを変更したくないだけかもしれず、行き先を韓国にし続けてきたことの問題の根が深いのか否かは分かりません。
先の九月記事でも申しましたが、朴槿恵大統領を「反日」から解放しなければ韓国の存続そのものが危ぶまれるのであり、あれからついに韓国の複数の新聞社が朴政権に対日融和を求める社説を掲載しました。
安倍晋三首相は内閣発足以来、一貫して対話の門戸を開いていることを韓国政府に伝えています。この戦略が奏功し、米政府は日本よりも明らかに韓国の態度に問題があると認識し始めました。
一方で、竹島の武装占拠を解除させず、歴史認識問題では、過去の内閣の誤った談話の程度に対しても態度を明確にしないからこそ、日韓対立の仕掛けを壊すことが出来ません。壊せないうちに、無責任な大人たちが対立利権に乗せられて生徒を韓国へ連れて行くとすれば、果たしてそこに教育的価値はあるのか、もう一度考えましょう。
【11.4 第9回憲法問題決起集会のお知らせ】
詳しくは真正保守政策研究所 公式ウェブサイトをご覧ください。
分類:亜州・太平洋関連, 日本関連 | コメント6件 »
皇紀2673年(平成25年)10月23日
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/131018/wlf131018……
▲産經新聞:「神在月」に神が降臨!? 3つの太陽、逆さ虹…
消費税増税・法人税減税が財政再建や内需(景気)回復、給与下落(デフレーション)解消に何ら効果がないことや、環太平洋経済連携協定(TPP)への参加交渉でわが国が妥協する必要は全くないことなどをいくら提言しても、「賢者に助言は要らない。愚者は聞く耳を持たない」とはよく言ったものです。
何度も申しますが、私は第一次安倍内閣、第二次安倍内閣のそれぞれ発足前から、一貫して安倍晋三衆議院議員を「首相に相応しくない」と批判してきました。
しかし、多くの皆様から安倍内閣への期待の声を伺い、ならば建設的な政策提言をもって安倍首相の方向性を「彼が口にした理想的な日本」に皆で誘導すればよいと私は考えましたし、TPP問題では西田昌司参議院議員らが安倍首相に解説してまでその危険性を伝えましたが、それでもまるで方針に反映されません。
一国の為政者が迷いすらない賢者である必要はありませんが、聞く耳を持たない愚者では困ります。それは約三年間にも及んだ民主党政権の三人の首相を見ても明らかでした。
何に耳を傾け、何を一蹴するか、それで為政者の目指す政治の方針が見えるものです。まず日本銀行と連携して経済を建て直すとした安倍首相は正しかったのですが、この期に及んで私たちの多くには安倍首相の目指す方針がどう見えているのでしょうか。
これまた何度でも申しますが、成長戦略こそが経済政策の要だったにもかかわらず、まるで「後出しじゃんけん」のようになり、そのくせ引き分けか負けの手を出して今のところ終わっています。最初に大きな衝撃を与えることが必要でしたが、資源政策の進展を目指す調査は行なわれず、減反政策からの完全な転換も打ち出さないまま、知的所有権の保護に関する対外行政の取り組みを決めもしないで、「クール・ジャパン」という言葉だけが「アベノミクス」のように上滑りしているのです。
島根県出雲地方で十八日、太陽の周りに光の輪を作る「内暈(うちがさ)」、三つの太陽を出現させる「幻日(げんじつ)」、逆さまの虹を描く「環天頂(かんてんちょう)アーク」と呼ばれる大気光学現象が全て同時に発生していたことが、分かりました。
本年五月十日、出雲大社は本殿遷座祭を執り行い、伊勢の神宮も十月二日と五日に遷御の儀が執り行われ、まさに「御遷宮」の年となりましたが、出雲では目下、全国から神神が集まるとされる「神在月」の時期を迎えており、この珍しい現象は本当に神神が降臨されたようにも見えます。
決して「変わったこと」を申すつもりはありませんが、多くの私たち国民が選択を誤り、約三年間を無駄に過ごし、御遷宮を前に人心一新、再び期待の旗手を為政者に据えてはみましたが、神神は私たちの迷いを見抜かれたのでしょうか。或いは、私たちがこの大気光学現象をそう捉えるような心理状態、すなわち新たな救いを求めていることを見抜かれたのでしょうか。
その救いの手は、私たちの中に降りました。特に日米中韓にあってわが国の孤立を狙った中韓をはね除け、強い経済力を回復させようとした安倍首相を救う手も、他力本願ではなく私たちの中に確かに降りたのです。
【11.4 第9回憲法問題決起集会のお知らせ】
詳しくは真正保守政策研究所 公式ウェブサイトをご覧ください。
分類:日本関連 | コメント3件 »
皇紀2673年(平成25年)10月22日
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131019/plc131019……
▲産經新聞:靖国神社 やはり首相は直接参拝を
靖國神社の秋季例大祭期間中の十八日または二十日、新藤義孝総務相と古屋圭司国家公安委員長、さらに超党派の「みんなで靖國神社に参拝する国会議員の会」の百五十七人(衆議院百十四議員、参議院四十三議員)が靖國神社を参拝しました。
内閣からは加藤勝信官房副長官のほか、西川京子副文部科学相らを合わせれば、実に百六十人以上が参拝しており、これは平成の御世に於いて過去最多の人数です。
しかし、産經新聞社が主張するように、安倍晋三首相が春季に続いて秋季例大祭でも参拝しなかったことは、それこそ国民にとって「痛恨の極み」だったかもしれません。
中韓両国は閣僚らの参拝に対しても批判し、特に中共の『環球時報』は「鬼を拝む右翼政治家の数は過去最高を記録した」などと口汚く書き立てています。つまり、安倍首相が参拝しなくても状況の好転はなく、日中・日韓の首脳会談も実現していません。ならば参拝しても全く問題はないはずです。
ところが、この問題で圧力をかけているのは米国であり、まず同盟国の理解を得る努力をしなくてはなりません。彼らはもはや韓国のためには何もしなくなりますが、自国の利益と絡んで中共のためにはわが国を牽制しておきたい案件があるのです。
それは米国から見て「簡単に止めさせられること」であり、自国の経済や安全保障に関わるようなことは逆に中共を牽制します。わが国の首相が靖國神社を参拝するというのは、米政府にとって「どうでもよいこと」なのでしょう。
或いは、連合国軍による占領統治で、靖國神社が昭和二十一年九月に宗教法人化されたように、大東亜戦争に於けるわが民族の驚異的な結束力が宗教によるものだったと誤解し、その精神性を骨抜きにしようとしてきた米国にとっては案外、近年「止めさせたくなったこと」なのかもしれません。
だからこそ、まずこの米政府の間違いを正し、日本首相に靖國参拝をさせないということは、合衆国大統領がアーリントン墓地を参拝しないよう厳命されるようなものだ、と理解させなくてはならないのです。
加害者と被害者の違いは対立し合った国家で当然二分しますが、為政者はまず自国民に説明出来ないような行いをすべきではありません。何度でも申しますが、現職の首相が過去の国民の犠牲を無視するということは、現世の全て国民に対しても同じ態度をとるということであり、到底私たちに説明出来る態度ではないのです。
同盟国を説得するためにも、米国内で浸透している中共を中心とした「反日喧伝」の信憑性を失墜させるべく、現地で連邦議員や連邦政府職員、大統領官邸に対しても話の出来る人材を雇い、政府は本気でいわゆる「親日喧伝」をしなければなりません。「日米同盟」の慢心の挙げ句がこの始末だからです。
そして、靖國神社に出来ることは、政府から見て「逆賊」の扱いを受けた先人たちの「国想う」戦死に対しても本殿合祀で応えることではないでしょうか。
私は、安倍首相について、「長期政権でいつでも参拝するという『外交カード』を中韓に対して切れる」と(安倍氏の再登板には反対し続けてきましたが、なってしまったからには政策提言として)好意的に分析してきましたが、いつまでも国民に説明の出来ない態度をとってほしくはないものです。
麻生太郎首相(当時)が記者団を叱って述べたように、靖國神社は本来静かに参拝するべき招魂社であり、天皇陛下の御親拝を賜るためには政争の具であり続けてはいけません。長期政権かどうかも分からなくなり始めた今、安倍首相自身のためにも臨時国会閉幕後から毎日参拝してはいかがでしょうか。
分類:日本関連 | コメント3件 »
皇紀2673年(平成25年)10月21日
http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/kaiken/gokaito-h2……
▲宮内庁:皇后陛下お誕生日に際し(平成25年) 宮内記者会の質問に対する文書ご回答
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131017/plc131017……
▲産經新聞:安倍首相と維新・石原氏が憲法改正で論戦、一方の民主は…
旧太陽の党(日本維新の会)の石原慎太郎共同代表は十六日、衆議院本会議の代表質問で、「現行の憲法に歴史的な正統性があるのか。ないなら、憲法の『無効』を明言したらよろしい」と迫りましたが、安倍晋三首相は「現行憲法は最終的に帝国議会で議決され、既に六十有余年が経過し、『有効』と考えている」と答弁してしまいました。
現行の占領憲法(日本国憲法)が帝国議会で議決されたのは、それが大日本帝國憲法第七十三条・七十五条の改正要件を満たしていないにもかかわらず、連合国軍による占領統治下の施策、或いは講和条約締結のためのやむをえない妥協に過ぎなかったからで、当時日本共産党の野坂参三衆議院議員でさえ草案を前にして占領憲法の無効を見抜いていたほどです。
つまり、今でも自前の憲法(大日本帝國憲法)に違反したまま、わが国は正統性のない基本法に従って国家権力が動いていることになります。年月の経過は正統性の弁明になりません。
仮に安倍首相の答えが正しければ、彼自身が懸命に取り組んできた北朝鮮による日本国民拉致事件に於いても、既に三十有余年が経過していることをもって「もはや拉致被害者は北朝鮮人民であって日本国民ではない」ということになってしまいます。
占領統治下で憲法が奪われたこと、北朝鮮によって何人もの日本国民が拉致されたことのいずれも、原状回復が当然であり、盗られたまま放っておくなどありえません。わが国が初めて占領統治を受けたのは事実としても、そのたった一度の敗北で全てを否定したままであることは、かねてより蔓延する「侮日意識」そのものです。
しかし、安倍首相こそが「戦後レジームからの脱却」を掲げた立派な政治家だったはずであり、その人がまたも同じ口で占領憲法を「護憲」してしまうとは、一体何事でしょうか。
そのような中、皇后陛下は御自身の御生誕の記念に際して、以下のような御言葉を文書にて発せられました。宮内庁が公開したものから重要な箇所を抜粋します。
——————————
かつて、あきる野市の五日市を訪れた時、郷土館で見せて頂いた「五日市憲法草案」のことをしきりに思い出しておりました。明治憲法の公布(明治二十二年)に先立ち、地域の小学校の教員、地主や農民が、寄り合い、討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案で、基本的人権の尊重や教育の自由の保障及び教育を受ける義務、法の下の平等、更に言論の自由、信教の自由など、二百四条が書かれており、地方自治権等についても記されています。当時これに類する民間の憲法草案が、日本各地の少なくとも四十数か所で作られていたと聞きましたが、近代日本の黎明期に生きた人々の、政治参加への強い意欲や、自国の未来にかけた熱い願いに触れ、深い感銘を覚えたことでした。
——————————
皇后陛下は、私たち臣民の間で憲法論議が盛んになリ始めたことを取り上げられ、大日本帝國憲法の制定過程で奮闘した先人たちのことを語られました。明治の当時から人権や自由の保障を巡る議論が活発になされていたことを私たちにも明確に思い出させるものです。
そこに占領統治下の連合国軍と政府の相互牽制の過程や、その後の憲法論議などは一切ありません。皇后陛下が思い出されたのは、あくまで大日本帝國憲法のことなのです。
天皇陛下も皇后陛下も、私たちの政治を御決めになる御立場ではなく、祭祀を司られる御立場であらせられますから、文書の御言葉以上のことは分かりませんし、御気持ちを詮索すべきでもありません。
ただ、私たちはその御言葉から真実を見い出すのみであり、わが国にあって正統性のある憲法とは何であるか、これで自ずと答えが出たではありませんか。
【11.4 第9回憲法問題決起集会のお知らせ】
詳しくは真正保守政策研究所 公式ウェブサイトをご覧ください。
分類:日本関連 | コメント7件 »