自衛隊内の下克上?左翼のせい?
東京都の石原慎太郎知事(当時)が沖縄県石垣市尖閣諸島に対する政府の態度に業を煮やし、都の所有計画を宣言したのを封じ込めるためだけに国有化した当時の民主党政権はその後、文字通り何もしませんでした。
あれから十三年。讀賣新聞社の記事は、ここで連日のように申してきたことの「まとめ」になっています。石垣の漁師さんたちを守る、私たち国民の領土を守る政策をめぐり、中共(支那)共産党に遠慮するなどあってはなりません。
国民を守らない、領土を守らないような政府は、政府ではないのです。政権が自民党(当時の安倍晋三首相)に戻り、私たちが「海上保安庁は石垣の漁船をこの海域から追い出すな」という訴えが通り、今では第十一管区海上保安本部(那覇市)の巡視船が毎日のように漁船の安全を見守り、中共産党(海警局)の武装船を追い出しています。
その活動は、石垣市議会の仲間均議員から漁業関係者の惨状を伺った時から始めたものです。あれから中山義隆市長の誕生(革新市政からの大転換)を支援し、今や「尖閣防衛」を当たり前にしましたが、先月十七日に五選を果たした中山市長の言葉にもお目通しください(産經新聞社記事を参照)。
■動画提言-遠藤健太郎公式チャンネル(YouTube)チャンネル登録お願いします!
最新動画【C国に抗議】実は共産党軍は日本と戦っていない?~日本改革党・せと弘幸候補
尖閣防衛の意思など微塵もなく国有化した旧民主党政権の残党・立憲民主党は、新執行部人事に着手し、幹事長に安住淳氏、代表代行に近藤昭一氏、選挙対策委員長に逢坂誠二氏を起用するという「自民党よりも悪手の『いつもの顔ぶれで回してます』」を発表しました。
報道権力を立法権力の末端(安住氏)が脅迫し、生粋の左翼・極左に党第二の顔を任せる野党こそが自民党の延命に手を貸してきたのです。「安い野党」が「安い与党権力」を生んできました。
私が先の参議院議員選挙で落選を惜しんだ浜田聡前議員は、日本自由党を結党して孤軍奮闘しています。日露戦勝百二十年の今月五日に、公表されました。
現下の国会には、浜田前議員のような多くの議員を「ハッ」とさせる丁寧な質疑のできる政治家がいません。躍進した参政党は、いよいよ力の見せ所です。
私が参政党応援の理由とした安藤裕議員の活躍に期待し、大いに自民党と財務省を揺さぶってもらいたいと思っています。
そこで最後に、八月二十一日記事で扱った防衛省・自衛隊内部の問題について、少し言わせていただきたいのです。先の記事では「自浄作用なき組織」との批判について述べましたが、それには大きな契機がいくつもありました。
陸上自衛隊朝霞駐屯地で起きたことの詳細がわからない以上、推測を交えながら申すほかありませんが、生意気な自衛官が組織の規律を無視して暴言を吐き散らしたというよりは、その組織の規律(上官の指示)自体に問題があったのでは、と。
この上官二名に問題があったかどうかもわかりません。しかし、処分を受けた一等陸尉が指弾せずにはいられなかった問題が自衛隊の中にあったはずです。
そもそも自衛隊が「パワハラだのセクハラだの」と言い出してから組織の規律がおかしくなり始めました。これは、誰が私にそう指摘したかについては伏せます。
以前に私が「氏(姓)に『五』のつく者を二度と防衛大学校や自衛隊に入れるな」と冗談交じりに申したことがありましたが、上官が下士官を暴力行為で虐待していいとは決して申していません。今回の場合は、むしろ下士官が上官に楯突いたわけです。
このようなことは、企業などでもよくあります。上司の指示や策にどうしても得心がいかず、意を決して反抗した経験は、私自身にもありました。
楯突かれた上官や楯突いた陸尉が悪かったというより、私たち国民が逃げ続けた現行憲法(占領憲法)論と、今回のような内部事情がわざわざ公表されたことといい唯唯諾諾と見逃し続けた左翼・極左のポリティカル・コレクトネス(綺麗事莫迦)が自衛隊に及ぼした悪影響の顛末ではなかったでしょうか。
次期首相が「誰になるか」という今、どうしてもこの問題を提起しておきたかったのです。





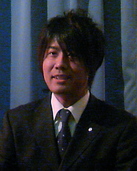
皇紀2685年(令和7年)9月11日 4:04 PM
今回の記事を読んで、「悪法も法なり」という言葉を思い出し、検索してみました。
AI による「悪法も法なり」の概要
「悪法もまた法なり」(あくほうもまたほうなり)とは、たとえその法が不当なものであっても、定められている以上は法であるから従うべきである、という意味のことわざです。古代ギリシャの哲学者ソクラテスが言ったとされる逸話が有名ですが、実際にはソクラテスの言葉ではない可能性もあり、ラテン語のことわざ「Dura lex, sed lex(法は厳しくとも、それも法である)」がその起源ではないかとも言われています。
意味
・どんなに不正な、あるいは道理に反する法律であっても、それが法として存在している以上は、人々はそれに従わなければならない、という意味です。
・法律に反対する場合は、法の廃止や改正を目指す適法な手続きを取るべきであり、単に不満を抱くだけでなく、建設的な行動を促す側面も持ち合わせています。
起源と背景
・この言葉は、古代ギリシャの哲学者ソクラテスが、アテナイの法に従って死刑を受け入れたというエピソードに由来すると伝えられています。しかし、ソクラテスの言葉としてプラトンの著作に登場する確証はなく、後世に広まったものという指摘もあります。
・ラテン語のことわざ「Dura lex, sed lex(法は過酷であるが、それも法である)」が、この言葉の源流ではないかという説もあります。
以上
また、次のような資料も。
https://gkbn.kumagaku.ac.jp/research/sw/files/2019/02/83b4aab55c47a4d0ad587c71ff968316.pdf
わたしの研究 58
本研究所研究員 森口 千弘(憲法・教育法)
「悪法も法なり」という言葉があります。どんなに正義に反する法であっても、法は法である以上従うべきである、という意味の言葉です。
悪法とまでは言わずとも、日常生活のルールの中で何かしらの違和感を感じるものは多いと思います。
たとえば、学校では髪を染めてはいけない、どんなに嫌な奴でも先輩には敬語を使わなければならない、給料は出ないけれど始業の15分前にはアルバイトを始めていなければならない、等々。
おかしいな、と思っても、社会の中には従うべきとされているルールがあり、それに従うことは美徳とみなされます。
戦前から戦後直後の裁判官、山口良忠は、違法なヤミ米を食べることを拒み、栄養失調で命を落としました。
彼はヤミ米を禁じた食糧管理法を「悪法」であると考えながらも、裁判官の立場からそれに背くことを潔しとしなかったのでした。この逸話は美談として語り継がれています。
けれども、内容を問わず「ルールだから」従う、という考え方は、時には人間としての感覚を麻痺させ、恐ろしい結果を生むことがあります。
法や上層部の命令に従ってユダヤ人虐殺に手をかしたアイヒマンの例は言うに及ばず、ここ日本・熊本でもハンセン病患者や優生保護法による不妊手術の強制など、「法に従って」人の人生を狂わせてしまうような事例が、つい最近まであったことを忘れるべきではありません。
私が法学の研究を始めた理由は漠然としたものでした。ただ、「悪法も法なり」「ルールなんだから従え」といった考え方への反発は、研究者の道を選ぶ大きな理由であったと思います。
この社会において、ルールを振りかざす人の大半は「偉い人」です。
それは国家権力であったり、学校の担任、バイト先の店長、サークルの先輩であったりします。
そして多くの場合、彼らは、その内容の正しさゆえに、ルールを振りかざしているわけではありません。
むしろ、自分の立場をより強くするために、弱い立場の人への支配をより簡単にするために、ルールを都合よく使っているのです。
前述の山口裁判官の話を、私は美談だとは思えませんでした。
仮に社会の大多数が「従うべきだ」と考えるルールがあったとしても、そのルールが間違っている場合もあるのではないか、そうであれば、そのルールが間違っていること指摘する役割を誰かが果たさなければならないのではないか。
紆余曲折はあったものの、今現在はこのような問題意識のもと、私は憲法学、中でも人権論を研究しています。
憲法の意義
憲法とはどのような法かについては、たくさんの学者が議論を展開しています。
ただ、現代の憲法学の中で、憲法は国家の権力を抑制し、多数派によって少数派が迫害されることを防ぐ機能を持つ、というのは一般的な認識であろうと思います。
そして、憲法が持つ権力への抑制機能は、上に書いた私の問題意識とつながります。
すなわち、憲法にリストアップされた人権を軸にして、国家や権力がやってはいけないことは何か、あるいは、民主主義で多数派となれないような人たちにも最低限保障されなければならない権利とは何かを考えることで、社会の不当なルールに対して批判を展開していくことができます。
「ルールなんだから守れ」という立場の強い人たちに、「そのルールは間違っている」と正面から言い返すことのできる典拠になるのが、憲法の人権条項なのです。
もっとも、この人権というものは突然自然発生的に表れたものではありません。
たとえば、つい80年前の選挙では女性は投票することが許されていませんでした。
アメリカでは黒人と白人のバスの座席が分けられ、ソドミー行為が禁じられるなど、公然と差別が残っていました。
2018年に我々が当然の人権と考えていることがらは、ほんの少し前までは「ルール違反」であったわけです。
となれば、2018年にルール違反だと考えられている事柄も、何十年か後には当たり前の「人権」となっているかもしれません。
憲法学の研究の役割の一つは、何十年後かの「人権」を拾い出していくことだと思います。
法律学者のしごと
ところで、法律学者が何をしているか、具体的なイメージがあるでしょうか。
よく法律を専門にしているというと、弁護士や裁判官のように実務に携わる仕事をしていると誤解されがちです。
残念ながら、私には司法試験を受験したこともなければ、合格する能力もありません。
法曹と呼ばれる人たちが多様な法を用いて社会の様々な問題にアプローチするのに対し、法学を研究する人間はより狭い分野についての理論の構築を行います。
私の専門は憲法です。憲法というと、平和主義を謳った第9条がよく知られていますが、私の主たる研究対象は第19条です。
この条文は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」というたった22文字から構成されています。
しかし、この条文の中には、歴史的な意味が多くこめられています。
たとえば、この条文を意義あらしめることにより、戦前のような国家による思想統制を排し、日本は個人が自由にものを考えられる国であろう、ということを宣言したものとして、この条文は理解できます。
とはいえ、この条文のポテンシャルは多様です。
たとえば、日本に兵役が導入されたとしても、この条文に基づいた良心的兵役拒否が認められると考えられます。
また、近年大きな問題となっている公立学校での国旗・国歌強制の問題も個人の思想・良心にかかわるものと理解されています。
しかし、現状この権利が十分に尊重されているわけではありません。
憲法研究者として私が取り組むのは、将来に向けて思想・良心の自由がもつ意義を明らかにし、強い立場の人間によりこの権利が踏みにじられることの内容、理論を構築していくことです。
以上(全文掲載)
この筆者が革新(左翼)か保守(右翼)なのか、この論述だけでは判然としませんが、「新型コロナウイルスパンデミック」以降、「国家権力の横暴」が加速度的に強まっていることもあり、国民目線で書かれているこの論文に概ね同感できます。
一方、日本国憲法には人権(私権)制限の根拠として「公共の福祉」が謳われています。
AI による公共の福祉の概要
公共の福祉とは、社会全体が共有する利益や幸福を指し、個人の自由や権利が他者との間で衝突する際に、それらの衝突を調整し、すべての人々の幸福や利益が最大化されるように権利の行使を制限する原理として日本国憲法などで規定されています。
具体的には、ある人の権利の主張が、他の人の人権を侵害したり、社会全体の秩序や利益を損なったりする場合には、その権利の行使が公共の福祉のために制限されることがあります。
公共の福祉の具体的な意味
・社会全体の共通の利益:社会全体にとって有益な利益や幸福のことです。
・人権の制約原理:本来、個人に保障されている基本的人権が、他者の権利や社会全体の利益と衝突する場合、その衝突を調和させるために人権を制約する根拠となります。
例
音楽の音量:
ある人が大音量で音楽を聴いて楽しむ権利(表現の自由)と、隣の人が静かに読書をする権利(静かな環境で生活する権利)が衝突する場合。
公共の福祉の役割:
この場合、Aさんは音量を下げるなどの配慮をすることで、他者の権利を侵害しないようにします。この譲り合いが「公共の福祉」の考え方です。
日本国憲法における公共の福祉
・第12条:保障された自由や権利は「公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」と規定しています。
・第13条:生命、自由、幸福追求の権利は「公共の福祉に反しない限り、最大限に尊重されるべき」としています。
このように、公共の福祉は個人の権利を完全に否定するものではなく、人権同士の調和を図るために、必要最小限の制約を正当化する原理として機能しています。
以上
現在の日本における大きな問題が「グローバリズムによる国家破壊」であるという認識がネットで大きく広まっていて、特に「日本人の人権」が、グローバリズム・グローバリストによって大きく侵害されていることに危機感を持っている人が増えていると思います。
「グローバリズムによる国家破壊」の大義名分として謳われる「地球規模の公共の福祉」としては、「地球のため」「人類のため」という「地球規模の綺麗事」、これにより国家主権を制限し、国家主権を超越した権力をWHOなど国際的組織に持たせようという「悪だくみ」が、コロナパンデミック以降あからさまになっています。
本来日本の問題ではないはずのアフリカの感染症エボラウイルスの研究をわざわざ日本で行う、それもわざわざ東京都心に研究施設を作る計画が、日本国民の意思を完全に無視する形で進められています。
これと連動して日本をアフリカのホームタウンにするとか、憲法の基本的人権が大幅に削除され、緊急事態条項が設けられようとしているとか、このままでは「地球規模の綺麗事」で人権軽視・人権無視の体制が構築されてしまいます。
特に日本国民というか日本人の人権が、グローバリズム・グローバリストに支配された日本政府により行われていることに気づいて危機感を持つ日本人が増えていると思います。
移民だの多文化共生など、日本人が望んでもいないのに日本政府が勝手に推し進めている現状は、民主主義国家ではなく独裁国家です。
現実的に可能性がある総理大臣候補の中で最もマシと思われるのが高市早苗氏しかいないのは仕方ないにしても、高市総理大臣が安倍総理大臣を超える「愛国総理大臣」になり、現状を打破できるとは到底思えません。
一人のスーパーマン・スーパーウーマンに期待したくなるのは人情として私もそうなのでわかりますが、安倍さんがそうであったように、グローバリストは手段を選ばず、そういう人物を物理的に抹殺してしまいます。
「出る杭は打たれる」ということわざがありますが、現在では「影響力がある目立つ愛国者は撃たれる」になってしまっています。
一般国民にはどうしようもない状況にみえますが、単純に論理的に言えば「影響力がない目立たない愛国者」を増やして数の力で極悪非道なグローバリストと戦うしかありません。
グローバリストが撃とうとしても、「狙いを定められないほどの大勢の愛国者」を形成することこそが必要だと思います。
高市総理大臣本人の活躍に期待するというより、高市総理大臣が「狙いを定められないほどの大勢の愛国者」を生み出す起爆剤になることに期待します。
皇紀2685年(令和7年)9月11日 6:49 PM
https://politician.cafe/politician/222/activity/10549/
日本保守党・島田洋一議員、小林鷹之氏を「宮沢増税会長の丁稚」と批判
日本保守党の島田洋一衆議院議員が、自民党総裁選に向けて出馬の意向を固めた小林鷹之元経済安全保障担当相を痛烈に批判した。島田氏は自身のSNSで「宮沢増税会長の丁稚こと小林鷹之氏も出馬の意向らしい」と揶揄。「増税路線に爽やか風の外貌を被せられる彼は、財務省にとってベストの候補かもしれない」と述べ、国民が望む減税の流れに逆行していると強調した。
さらに島田氏は「通常国会終盤、衆院財務金融委員会で与党筆頭理事を務めた小林氏が、ガソリン減税法案潰しの先頭に立った」と明かし、国民生活を直撃する物価高対策に背を向けた姿勢を厳しく非難した。
「小林氏がガソリン減税潰しをしたことを忘れてはいけない」
「爽やかさの裏に隠れた増税路線は危険」
「財務省にとって最適でも国民にとって最悪」
「民意は減税だ、逆行する候補はいらない」
「宮沢税調会長の路線を継ぐ人は総裁にふさわしくない」
SNS上では「国民の声を無視した増税候補」との批判や「見た目でごまかされるな」という警戒の声が広がっている。(ここまで引用)
学歴エリート 単にそれだけの人物であって、日本の歴史の真実も知らず、だから、今現在の日本国・日本人の 真の政治課題 生命をかけても達成すべき「主権と独立の 真の回復」など全く認識できない 考えたこともない者。歴史を作る能力の無い者。議員に値しない。
皇紀2685年(令和7年)9月11日 9:08 PM
もうずっと以前、何回かまえの選挙のとき、
近藤昭一落選運動のチラシをポスティングしたことがありました。
ある商店で、店主がちらっとチラシを見て「あいつは北朝鮮のスパイだ」
と吐き捨てるようにおっしゃいました。知っている人は知っているんだな、と。
そのときの選挙では近藤氏は落選しましたが、そのとき当選した自民の政治家が
あまりパッとしなくて。しかも例の政治資金でケチがついて辞めています。
この選挙区ではずっと近藤昭一の天下です。
この選挙区の人は、どうしてこんな人を支持し続けるんですかね。