消えた主食21万トンを追え!
一月三十日記事と三十一日記事で取り上げた沖縄県教職員組合(沖教組)の脅迫事件にも繋がるのですが、沖縄県庁が起こした「株式会社ワシントン事務所」事件でも、大浜一郎県議会議員の「公務員の身分で政治活動をしていいのか」という問いに長嶺元裕基地対策課長が「特段の問題はない」などと平然と答えています。
何を言うか! 立派な地方公務員法違反です。
産經新聞社記事は、公務員の氏名をいちいち伏せていますが、ここではすべて公開します。長嶺氏が法律違反を「問題ない」と吐き捨てたからには、そうした認識で誰が犯行を教唆したのか、或いは幇助したのか、もはや国家次元で明確にしてもらわなければいけません。
新垣淑豊議員が呆れかえったように、多くの県民にとって公金の不正支出が問題の焦点であるにもかかわらず、まともに答弁できない県庁側は、前知事の翁長雄志氏から現知事の玉城康裕(芸名=玉城デニー)氏に至るまで、その下で一体何をしてきたのですか。
最もしどろもどろになった「ロビー活動の違法性」について、工作活動の内容によっては、刑法第八十一条違反(外患誘致罪 量刑は死刑のみ)の可能性すらあるからで、この一連の事件は、すべて国民が被害者になりうるのです。
■動画提言-遠藤健太郎公式チャンネル(YouTube)チャンネル登録お願いします!
最新動画 【大阪】梅田の由来になった神社に何でこんなものが?
さて、一月二十七日記事で扱ったコメの高騰ですが、何と二十一万トンものコメが行方不明になっているというではありませんか。
つまり、流通過程のどこかで、それが阻害されているわけです。農林水産省が調査すると言っていますが、全国農業協同組合(JA)と農林中央金庫を含むJAバンクが「中抜き」の実態を隠しているに違いありません。
農家は、売ったコメが流通したその後を知りませんし、たとえ売った価格以上の値がのちについても、農家の収益にはならないのです。農水省のいう二倍近い値上がり(令和五年との比較)で、農家は得をしておらず、消費者はただ損をしています。
安倍晋三元首相が平成三十年、食糧安全保障を掲げて減反をやめさせましたが、コメ価の下落を嫌悪するJAが供給計画を常に少なく見積もり、コメから転作する農家へ補助金まで出す事実上の減反を続けてきました。
決して少なくなかったはずの令和五年の収穫に対し、昨年の収穫分は、既に奪い合いの結果として少なくなっており、延延とコメ不足が続いているのに加えて「二十一万トンがどこかで止まっている」のでは、中間業者にも調査対象を広げて実態をあぶり出すしかありません。
これは、外国人観光客の増加による需要増だの地球温暖化だのとは何の関係もなく、確実に農政の構造的問題です。新自由主義の跋扈で、軽薄なまでの「農業はオワコン。農産品は外国産をカネで買えばよい」などという暴論がまことしやかに扱われたことによる問題も、決して無視できません。
農水省は、未だ「コメ不足」を深刻には認めておらず、備蓄米の放出にしても、政府が買い戻す条件をつけています。あくまでJAのコメ価操作に加担する気です。
国民のための備蓄米政策になっていない現状は、まさに現行憲法(占領憲法)政治がもたらした出鱈目の反映でしかないのです。




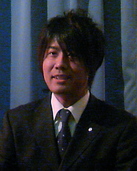
皇紀2685年(令和7年)2月2日 3:47 PM
250202―3 順法精神の欠如が地方公務員にも広がっている実態は危機的です
遠藤さん今日は ソロです。
まず沖縄のワシントン事務所開設を株式会社で行っているという奇異な行動と、一体ワシントンの何処と呑あ行賞形取引をして「金儲け」ヲ明らかにせねばなりません、そう言う意味で100条委員会を開設して追及するは宜しいのですが、かっ質問された議員が公務員法有藩の事案なのに「問題ない」と言う認識では、遵法精神の欠片も無いので、話にならない。
このレベルの法律知識で、県議会議員が務まるのなら中学生でも務まると思いますが、当然辞職して頂く話に成るでしょう。然し、事はア遠藤さんが仰しゃる様に単なる公務員法違反の話では無く、本来国家同士の安全保障の範疇に有る沖縄の米軍基地問題なので、其処に、地方行政体が国家を飛び越えて話をすれば、その内容に因っては外観誘致罪の適用も有る。
此の件は固より、地方行政体自体がさよぅ極左団体の巣窟と化している事が原因ですg¥から、先ずは、共産系の帰化人を排除すべきで、遡って、帰化取り消しもありうると、法律を改めるべきだと思います。 すると、この時点でも、翁長前知事も神経帰化人の噂がありますし、現知事の玉城デニ-も韓国系帰化人ですね。
斯う言う今迄隠して来た経歴がバレて、今迄築いて来た社会的忠を喪う時代に成ったのです。 何でも、物理学の作用反作用の野法則は生きているのです。 なので「差別だぁ」と言う抗議は一切認められません。其れを言うなら自分こそ、日本人を散々差別して来たのでは無いので歯無いですか?
特に生井沢一郎さん貴方は「背の李移民」だと言われていますが、真偽の程は別問題として、自民党に中で闇の「陸のフィクサ-」として、3人の総理大臣を職に就けたが、自身は総理大臣委はならず、90年に自民とを割って出て新進党を創立御少なくない自民党議員を引き抜きましたね。 結局この反乱は実を結ばず党は解党したが爾来惑星のような存在です。
然し、結果として貴方が政治家として何をしたのか、何を成し遂げたのか、誰が貴方を評価出来るのか? 答えは空しいですね。貴方が沖縄知事に引っ張り込んだ玉城デニ-も、今回の100条委員会の追及が届けば弾劾される可能性もありますよね、その時も塩、貴方にお関係が歌ああが割れたら、生き恥を曝す事にもなあり兼ねませんよ。
貴方こそその遵法精神の貧しさを糾弾されるのにふさわしい人はいないと私は確信しています。 例え貴方が何人でも低いモラルで汚い金を稼いで億万長者になった事実は隠し様が無い野ですからね。まさに、これから「何時までも有ると思うな親とかね、無いと思うな運と天罰」と言う俚諺を噛み締めて、余生を送る事に成るのを願っています。
扨「消えた新米21万トン」の話しですが「オソラク現物は鮒済みしてシナへ運ばれて、既に売り捌かれてこの世に無いか、シナの倉庫で眠っている」のだと思いますから、取り戻すのは粗不可能でしょう。 此処にもシナとDS との繋がりの可能性が有り、是が表沙汰になれば、ロシアとシナの間亜が忽ち緊迫化する事案に繋がりますね。
いわば、DSが仕組んだ露ウ戦争解決阻止の紛れだと思いますね。勿論私の推測に過ぎないのですがもし当たって居たら、世界がシナとは関係を断つので、世界からシナが消え去る羽目になるかも知れない。 紛れは日本を巻き込むのでトランプ政権から大事なパ-トナ-の日本を引き剥がしに懸かっていると言う事だが、台湾も巻き込む虞が有る事案だ。
兎に角、追い詰められた者同士、祖に御真意が見えない形で、悪あ足掻きそのものを始めていると私は解釈しています。 こうして眺めれば、世界は歴史の浅い把握人文明と歴史が存在し無い遊牧民国家のモラル面で進化無き絶滅~消滅の前の悪足掻きそのものを辟易する程見せ垂れていますね.今度の小氷期で人類は何処迄人口を減らすのかなぁ?
皇紀2685年(令和7年)2月2日 3:56 PM
農協は設立は各地方で地域の人の出資で行われた。次第にボス的な人が選ばれて権力を握り当初の協同組合から大きく逸脱した組織になってしまった。農民に利益を与えるのではなくもはや協同組合ではなく利益追求会社と変貌している。戦後機械化が進むにつれコメを一手に扱い、金融会社もしくは商社に変化してきておりすでに協同組合としての役割は終わっております。解体すべきではないでしょうか。